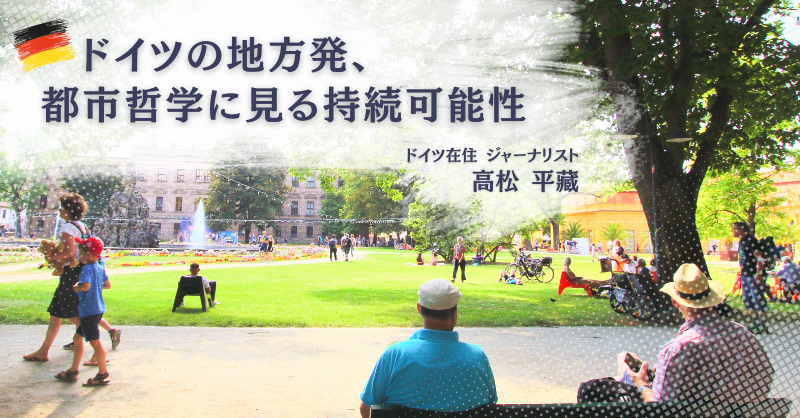 |
「スマートシティ」という言葉は、もはや耳慣れたものとなった。ドイツの自治体でも、インターネットの高速化やAI、IoT(モノのインターネット)、クラウドといった技術基盤が整い、スマートシティの実装化が徐々に進んでいる。しかし、技術とはあくまで人間の「道具」に過ぎない。技術が進歩すればするほど、都市の根幹を成す都市哲学の重要性が増してくる。
■スマートシティとはどんな機能を持った「都市」か?
スマートシティとは、一体どんな都市なのだろうか。それは、次の3つの要素を備えた都市だと言える。
(1) データ収集と処理:これは「素材集め」に相当する。都市全体にセンサーやカメラを設置し、交通流、環境条件、エネルギー使用量など、都市活動に関するデータを常時収集する。これらのデータは、クラウド技術を用いてリアルタイムで保存、転送、分析される。
(2) インテリジェント・インフラストラクチャ:これは「素材をもとにツールをうまく活用すること」だ。交通管理システムではAIを活用して信号機を制御し、渋滞を軽減する。エネルギー管理ではスマートグリッドを導入し、再生可能エネルギーの統合や需要に応じた供給調整を行う。センサー付きのゴミ箱を導入し、効率的な廃棄物管理を実現することも可能だ。
(3) 先進的なアプリケーション:これは「集めた素材をもとに自治体の未来をみんなで考えること」にあたるだろう。例えば都市全体のデジタル上の複製である「デジタルツイン」を作成し、さまざまな都市開発シナリオをシミュレーションできる。自動運転車両の導入や、拡張現実(AR)を活用した都市計画ツールの開発なども進められる。市民参加型のプラットフォームを構築し、都市の意思決定プロセスに市民の声を反映させることも重要だ。
これらの要素が統合されることで、スマートシティは効率的で持続可能な都市へと進化する。
■スマートシティは大都市だけのものではない
ドイツのスマートシティ化の現状を概観しておこう。デジタル業界団体Bitkomによる「スマートシティ・インデックス」は、82の主要都市を対象に、デジタル化の進捗状況を評価している。調査項目は「行政」「ITと通信」「エネルギーと環境」「モビリティ」「社会と教育」。この5分野と「総合」によるランキングが出される。2024年の最新調査では、ミュンヘン(人口160万人)が首位を維持し、ハンブルク(190万人)、ケルン(110万人)がそれに続く。
 スマートシティインデックス2位のハンブルクの市庁舎。19世紀に作られた建造物で「先祖が勝ち得た自由を、子孫が誇りをもって守り継ぐべし(中央の金色文字)」と記されている。テクノロジーが進んでも都市の価値観は変わらないことを示しているかのようだ(筆者撮影)
|
このランキングからも、スマートシティとは最先端技術が実装された巨大都市を想像される方が多いかもしれない。しかし、ボーフム(36万人 4位)、フライブルク(24万人 6位)、リューベック(22万人 8位)といった中規模都市も、それぞれの強みを生かしてランキング上位に食い込んでいる。
これらの都市において、行政分野では、オンラインでの手続きや電子決済が普及し、市民サービスの利便性が向上している。エネルギーと環境分野では、再生可能エネルギーの導入や省エネルギー化が進められている。ITと通信分野では、光ファイバー網の整備や5Gの普及が進み、高速通信環境が整備されている。モビリティ分野では、スマート交通システムやシェアリングサービスの導入が進み、移動の効率化が図られている。社会と教育分野では、デジタル化を推進するための人材育成や、市民参加型のプラットフォームの構築が進められている。
重要なのは、各都市がそれぞれの地域特性や課題に合わせて、デジタル技術を活用している点だ。画一的なスマートシティモデルではなく、多様なアプローチが存在することが、ドイツのスマートシティ化の特徴と言えるだろう。
さらに小規模自治体でも都市全体のデジタル上の複製である「デジタルツイン」技術が活用されるケースが出てきている。例えば、バイエルン州のフォルヒハイム市は人口わずか3万4000人程度だが、「デジタルツイン」を導入し、都市全体の可視化や意思決定の効率化を図っている。これは、スマートシティ化が単なる技術導入ではなく、都市運営の効率化や市民生活の質の向上を目指すものであることを示している。
スマートシティ化は、規模の大小に関わらず、すべての都市にとって重要なテーマとなっている。それぞれの都市が持つ個性や課題を理解し、デジタル技術を適切に活用することで、持続可能な都市の実現に近づくことができるだろう。
■新ライプチヒ憲章と技術
スマートシティの方向性を示唆しているのは、2020年に改定された「新ライプチヒ憲章」だ。この憲章は、都市開発における価値観の重要性を強調している。持続可能性、社会的包摂、公正な都市開発といった価値観を重視し、技術はそのための手段として捉えている。ドイツ政府は、自国のスマートシティ戦略およびプログラムにおいて、この憲章を明確に参照している。また、この憲章を、未来志向の都市開発にとって不可欠な原則と価値を定義する枠組みとして認識している。
テクノロジーは変化しても、この憲章が示すように都市の方向性を決める基盤となる価値観は変わらない。都市とは、市民と共に都市の価値を創造し続けるプロセスであり、永遠のベータ版と言える。スマートシティは技術の集合体ではなく、市民と行政が共に未来を築くためのプラットフォームといえよう。
ドイツのスマートシティは、技術革新と都市哲学のバランスを取りながら、持続可能な都市の実現を目指している。テクノロジーはあくまで道具であり、都市の価値観こそが、スマートシティの未来を方向づける。

高松 平藏 (たかまつ・へいぞう)
ドイツ在住ジャーナリスト
ドイツの地方都市エアランゲン市(バイエルン州)および周辺地域で定点観測的な取材を行い、日独の生活習慣や社会システムの比較をベースに地域社会のビジョンを探るような視点で執筆している。日本の大学や自治体などでの講義・講演活動も多い。またエアランゲン市内での研修プログラムを主宰している。 著書に『ドイツの地方都市はなぜクリエイティブなのか―質を高めるメカニズム』(学芸出版)をはじめ、スポーツで都市社会がどのように作られていくかに着目した「ドイツの学校には なぜ 『部活』 がないのか―非体育会系スポーツが生み出す文化、コミュニティ、そして豊かな時間」(晃洋書房)など多数。 高松平藏のウェブサイト「インターローカルジャーナル」















