ヤマハ発動機執行役員CSO(Chief Strategy Officer) 経営戦略本部長・新規事業開発本部長
サステナブル・ブランド国際会議 アカデミック・プロデューサー
 |
オートバイメーカーとして知られるヤマハ発動機が、モビリティを通して「人はもっと幸せになれる」可能性を追求する会社として、サステナビリティ経営の社内浸透を推進している。日本楽器製造の新規部門として生まれ、今年創業70周年を迎える同社は、国内外の二輪車レースで結果を残しながら成長し、船外機やゴルフカート、スノーモービルなど、独自のエンジン製造技術を軸に、幅広い乗り物を展開してきた。
1990年からは「感動創造企業」を企業目的として掲げる同社は今、その言葉をどのように再定義し、ヤマハ発動機らしいオープンな企業風土を生かしながら競争力を高めようとしているのか。間近に迫った「サステナブル・ブランド国際会議2025 東京・丸の内」の基調講演に登壇する、同社執行役員 CSO 経営戦略本部長の青田元氏に、青木茂樹・サステナブル・ブランド国際会議 アカデミック・プロデューサーが話を聞いた。
異業種を包括する「ヤマハブランド」の価値
青木茂樹 サステナブル・ブランド国際会議 アカデミック・プロデューサー(以下、青木):まずはヤマハ発動機の歴史について改めて教えてください。
青田元 ヤマハ発動機執行役員経営戦略本部長・新規事業開発本部長(以下、青田):ヤマハ発動機はもともと、後にヤマハとなる1897年創業の日本楽器製造から、1955年にモーターサイクル部門が社内新規事業として分離した、いわばスピンオフベンチャーです。モーターサイクル開発においては後発でしたが、創業からわずか10日後に開催された当時日本最大の二輪レースに第1号モデル「YA-1」を投入、優勝を勝ち取るなど国内外のレースで結果を残しながら成長し、船外機やゴルフカート、スノーモービルなど、エンジン製造技術を軸として幅広い乗り物を展開してきました。
青木:楽器のヤマハとは、現在どのような関係性にあるのですか?
青田:一言でいうと、ヤマハブランドは共有資産となっています。2社で合同ブランド委員会を組織しており、新しい事業にヤマハの商標を付ける場合には、両社が確認する作業が入ってくることになります。楽器とエンジンで、ターゲットは全く異なりますし、事業としての共通事例も過去にあまりなく、ブランドを分けることが実際に議論されたこともありますが、そうはなりませんでした。我々が歴史的に目指してきた願いとは、一つのブランドで多様な商品や産業を包含するという力を育てることであり、「いろいろなことをやっている」ことが人を惹(ひ)きつけることにつながると思っています。
通常、ブランディングは何か一つの方向に尖らせてストーリーを作るのが主流ですが、うちは逆のストーリーを作ってきたわけですね。これを続けていくことで、何かアウトカムが出ると信じていますし、逆に言えば常に未知の期待感を作り続けなければいけないと思っています。
青木:一つのブランドを共有しながら、全く別の事業を展開する事例は国内にもほとんどありませんね。オートバイに関しては国内主要4メーカーと言われますが、特にヤマハ車にはどのような特徴があるのでしょうか。
青田:歴史からひもとくと、「軽量で小型コンパクト」が我々の最初のアイデンティティーだったと思います。現在も私たちは「人機官能」という開発思想を掲げていますが、これは人と機械を一体化し、人の「悦び」を生み出すという考えです。「直線でのスピードが速い」といったアピールポイントよりは、「意のままに操れる」という骨格が受け継がれているように感じます。
ヤマハらしさを表す「感動創造企業」であるために
 |
青木:ブランドコミュニケーションとしては、ヤマハ発動機は「感動創造企業」という企業目的を掲げています。この感動というワードにはどんな想いを込めているのでしょうか。
青田:「感動創造企業」という言葉は1990年から使っているのですが、想像以上に自分たちの企業活動を体現するにふさわしい言葉だと思っています。この企業理念を理解するためには、「感動ってなんだろう」「お客さまからはどう見えているのだろう」と、形而上学的な問いに向き合い続けなければいけません。その点、ヤマハ発動機の社員は、普段のものづくりにおいても「このモデルはどういう方向を目指そうか」「この製品はどう使われているんだろうか」という問いに対して、言葉で伝え合うのが日常茶飯事なので、もう一つ上のレベルの「自分たちヤマハはどうあるべきか」というメタ認知的な部分でもできるはず。実際、非常にこうした思考が得意な会社だなと感じています。
青木:なるほど。「感動創造企業」をあえて因数分解するなら、具体的にどんな状態を目指すことになるのでしょうか。
青田:実は悩みどころでもあります。現在では連結で約5万人の従業員を抱える大組織になり、どうやって利益を最大化するか、どうやってコストダウンするかばかりを考えていると、どんどん「普通の会社」になってしまいかねない。しかし自分たちの商品開発の歴史をひもとけば、やっぱり熱いマインドを持った先人たちが挑戦を重ねてきた会社のはず。黎明期を支えた社員が引退してしまった今、このマインドの継承に対して危機感を抱いています。今こそ「感動創造企業」を再定義するタイミングだと思っていますし、過去に我々がやってきた他社との差別化、価値の作り方に本気に向き合い、創業以来の歴史と文脈を活かしながら新しいイノベーションを生む組織にしていくことが大切だと思っています。
青木:「感動創造企業」の実現に向けて制定された、「ART for Human Possibilities」についても教えてください。
青田:2018年に発表した、2030年に向けての長期ビジョンが「ART for Human Possibilities」で、アートとヒューマンという不確定な2つの言葉を置いてみたものです。「感動創造企業」に付随する「ヤマハらしさ」として「発・悦・信・魅・結」の5つの漢字を定めていたのですが、特徴的なのは「悦」と「魅」。目の前の仕事に没頭して向き合うことや、お客さまを惹きつける魅力のことですね。こうした極めてサイエンスではない、どこをKPIとすればいいのかもよく分からないものを追求していくという行動を、全社で言語化したのが「ART for Human Possibilities」です。
青木:「ART for Human Possibilities」の日本語のタイトルは「人はもっと幸せになれる」としていますね。
青田:誤解を恐れずに言えば、商品を売るということはお客さまの欲求に答えを出すことなんですね。モーターサイクルも船も、A地点からB地点へ行きたいというニーズを埋めるためのものであって、一番早く行きたいのか、安く行きたいのか、楽に行きたいのか、こうした目の前の「Googleマップ的な」課題に応えるモビリティづくりならば、分かりやすいストーリーです。しかし、感動創造企業ならもっとお客さまの潜在的な欲求に寄り添わないといけない。Googleマップでルートを検索しても、「一番楽しい、心地よいルート」は出てこないわけで、こうしたニーズに向き合うことでブランドとして差別化していきたいと考えています。
 |
青木:「幸せ」というのは本当に全方位的で抽象的である一方、事業は細分化され、(部署や社員が)それぞれの機能を果たしていかないといけませんよね。こうした10年ビジョンの社内浸透や活用に向けては、社員研修も行っているのでしょうか?
青田:特別な研修はやっていませんが、「人はもっと幸せになれる」を考えるためには、現状の立ち位置と、次に向かう場所がどこなのかを、それぞれ言語化する必要があります。長期間継続しているビジネスの中で、途中でバトンを受け取った担当社員だけではなかなか意識しにくい点ですが、それでも、「ART for Human Possibilities」「人はもっと幸せになれる」という言葉の存在自体が重要だと感じますね。商品開発や展示会出品時など、さまざまな場面でたくさん使っていくことで、社員たちの頭の何処かに残ってくれるし、意識してくれていると思います。
そもそも感動とは相手の想定・期待を上回った時に発生するというメカニズムで、これにたどり着くためには、努力して相手の期待を超えるか、相手の期待を下げるかの2パターンがあります。厳しいKPIを置いてしまうとどうしても後者のやり方に近づいてしまうので、我々はなるべく抽象的な言葉と社員同士の問いや対話を重ねることで、前者の方法を進めたいと思っています。
「非財務」価値とは、まだ顕在化していないだけの「未財務」的な価値
青木:今年2月に発表された新中期経営計画の中では「モビリティの楽しさ」「豊かな人生」「地球との共生」という3つのアウトカムを設定されています。これは、改めてどのような方針を定めたものでしょうか?
青田:「感動創造企業」であるために、経済的価値だけでなく、心躍る移動体験のワクワク感と、歳を重ねても安心して乗ることのできる安全性、脱炭素・循環社会への貢献などを追求していくことを示しました。
具体的に、気候変動については、企業活動における自社のCO2排出量を2027年までに2010年比 74%の削減、2035年にカーボンニュートラルを目指します。資源循環についても2050年までにサステナブル原材料使用比率100%を目指し、新中期では、現状の14%から18%に引き上げることを発表しました。さらにグローバルエンゲージメント指標を導入し、人的資本経営についても高いレベルを維持していきます。DE&Iの推進に加え、タレントマネジメントでは一人ひとりの育成計画にマッチしたグローバル人財プログラムを拡充することを定めています。
こうした価値は、現在は「非財務」とされるかもしれませんが、私はまだ顕在化していないだけの「未財務」的な価値と考えています。企業目的、アウトカム、2030年ビジョンの設定を通し、未財務的価値の指標をトラックしていきたいし、それを通して会社を支える人材を育成していきたいです。
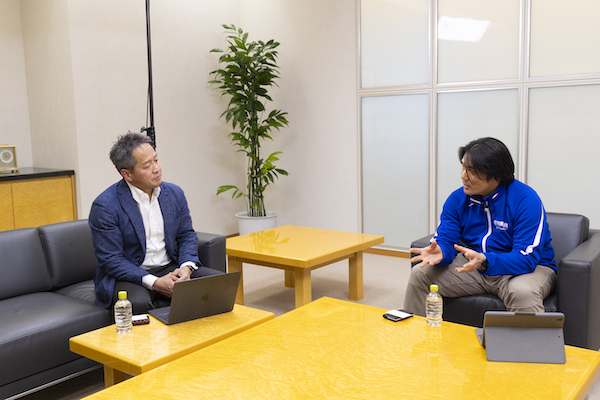 |
青木:ヤマハ発動機は海外売上高比率が約94%であることも特徴です。現状、コア事業としてモーターサイクル事業、船外機などのマリン事業を置きつつ、ロボティクスをはじめ戦略事業も展開されていますが、今後の事業拡張のイメージをお聞かせください。
青田:ヤマハブランドがより広い分野を拾える可能性に着目し、ここ5年ほどは、医療や農業の分野で新規事業を開発してきました。それ以外には、モーターサイクルビジネスの拡大ですね。モーターサイクルは平均単価が約2000ドルと決して安くはない商品ですので、キャッシュで買える人はそれなりに限られています。そこで、例えばフードデリバリーのプラットフォーマーと連携し、運転手の仕事をしたいけれど車両を持っていない・ローンも組めないという人向けにモーターサイクルを貸し出し、そしてそれを使って仕事をしてもらうという仕組みを、インドとナイジェリアですでに展開しています。新たなモーターサイクル利用者が増えること自体に価値があるので、相手のニーズに合わせて、他社製品を積極的にリースしている点が特徴ですね。
また、モーターサイクルの電動化も進めていきます。ヤマハは電動アシスト自転車を世界で初めて商用化した実績がありますし、電動スクーターや車椅子も含め、ノウハウを持っていますので。我々は2035年にはモーターサイクル販売台数のうち20%を電動化したいと目標を立てていて、各国の政策や電気価格などによっても事情が大きく変わる分野ではあるのですが、一般論としてはスクーターなどの小さな車両から電動化が進んでいくことになると考えています。
青木:なるほど。オートバイは、乗らない人にとっては「危ない」「うるさい」といったネガティブな印象も多いかもしれないですが、その価値への理解を促して顧客を増やすことは重要ですね。
青田:おっしゃる通りです。これに対しては、マイナスイメージをゼロにする動きだけでなく、モーターサイクルだからこその価値を説明していく必要があると思うんです。例えば我々の会社でモーターサイクルで通勤している社員は、行きと帰りのルートが違うことがあるんです。行きは一番早い方法、帰りは一番気持ちいい方法で帰っているわけで、これは車にはない、モーターサイクル特有の価値だと思っています。「面倒くさい乗り物だけど、間違いなく気持ちがいい」ことが財務的価値につながるかは分からないですが、少なくとも豊かな生活、より幸せな状態には近づいているはずです。
サステナビリティを企業のバイアリティ(生存性)だと考えるなら、我々はこうした魅力を、乗らない人も含めて伝えていかねばならないと思っています。そのためにはやはり、乗車による何らかの変化を実際に計測し、開示することが必要だと思っていますが、どうすれば乗らない人にそのメッセージが届くのか、検討を重ねています。
「人機官能」「意のままに操れる」というアイデンティティーをご紹介しましたが、これはビジネス的には非常に弱いんです。「乗ってもらえば分かる」ではなく、本来は見ただけで分かる、ウェブサイトを見ただけで感じられる、というものが無いと、メッセージとしては不十分ですから。この部分は、今後もコミュニケーションスキルを鍛えていきたい部分です。
青木:改めて、企業目的の社内外への浸透に向け、今後の展望をお聞かせください。
青田:我々のような大企業が持つ一番のアセットは、歴史だと考えています。今後設立70周年・75周年を迎えていくに当たり、今一度自分たちの歴史を振り返り、過去から学んでブランドを引っ張っていく作業を進めていきたいです。向かう方向性の矢印をピボット(転換)するのは、我々より圧倒的にスタートアップのほうが得意なわけで、我々は矢印をしっかり固めていきたいと考えています。
普通なら、大企業へのエンゲージメントを高めることは非常に難しいことのはずですが、幸い、ヤマハ発動機には、自分の会社や商品を愛している自発的な社員が驚くほど多くいます。逆に、「感動創造企業」「ART for Human Possibilities」といったメッセージや中期経営計画の発表によってトップダウンの色が出てしまわないように、社員の思いやモチベーションを大切にしながら、企業活動の方向性を整えていきたいですね。
文:横田伸治 写真:原 啓之

ヤマハ発動機株式会社
経営戦略本部
執行役員 CSO、経営戦略本部長 兼 Yamaha Motor Ventures Chairman
1996年三井物産株式会社入社。主に金属資源の投融資案件の組成、トレーディング業務を担当。デトロイト、ニューヨーク、ロンドンで合計10年の海外駐在を経験。2010年にハーバードビジネススクールのリーダーシップ開発プログラム(PLD)を終了。2017年にヤマハ発動機株式会社に入社、経営企画、新規事業関連業務を担当し、2024年から執行役員新事業開発本部長、2025年1月から現職。CVC活動の中心であるYamaha Motor VenturesのChairmanを兼務。

サステナブル・ブランド国際会議 アカデミックプロデューサー
駒澤大学経営学部 市場戦略学科 教授
1997年 慶應義塾大学大学院博士課程単位取得。山梨学院大学商学部教授、University of Southern California Marshall School 客員研究員、Aalborg University Business School 客員研究員(2022年4月〜2024年3月)などを歴任。
多くの企業の新規事業の立ち上げやブランド構築に携わる。地方創生にも関わり、山梨県産業振興ビジョン策定委員、NPOやまなしサイクルプロジェクト理事長。人財育成として、私立大学情報教育協会FD/ICT活用研究会委員、経産省第1回社会人基礎力大賞を指導。やまなし大使。















