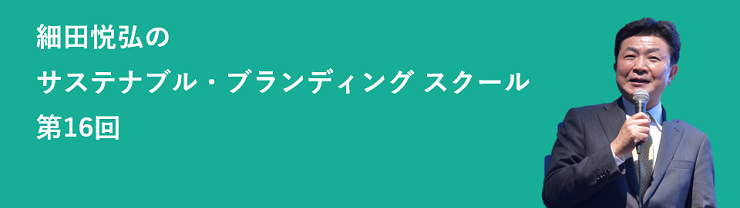 |
火曜ドラマ『私の家政夫ナギサさん』(TBS系)が好評のうちに最終回を迎え、高視聴率と称賛の声とともに、有終の美を飾りました。このドラマには、ウィズコロナ時代にふさわしいマーケティング・ブランディングのヒントが盛り込まれています。
コロナ禍で注目のドラマ
新型コロナウイルスの影響で混乱を極めたテレビドラマは、延期・中断・短縮・再放送とさまざまな策が講じられました。そのような状況下の注目作として、TBS系列『半沢直樹』と『私の家政夫ナギサさん』が挙げられます。『半沢直樹』がストレスを貯めに貯めた末、「倍返しだ!」で発散し解消するのとは逆に、『ナギサさん』はストレスフリーなドラマです。
 |
このドラマは、製薬会社の医薬情報担当者(MR)として仕事一直線の女性の主人公・相原メイが、苦手な家事をサポートしてもらうために「おじさん家政夫・ナギサさん」を雇うことから巻き起こるハートフル・ラブコメディーです。有能な家政夫・ナギサさんが、主人公のストレスを根こそぎ払ってくれて、それを見ている視聴者のストレスも解消されます。本連載コラムの前回は『半沢直樹』を取り上げましたので、今回は『私の家政夫ナギサさん(わたナギ」)』に着目しましょう。『わたナギ』が放送されている火曜ドラマは、今もっとも勢いがあるドラマ枠と言われています。このドラマには、サステナビリティ時代にふさわしいマーケティング・ブランディングのヒントが盛り込まれています。
 |
スーパー家政夫とマーケティング・ブランディング
製薬会社のMRでプロジェクトリーダーでもある多部未華子さん演じる主人公メイは、仕事に追われて部屋が片付きません。そこで彼女の誕生日に、家事代行サービス会社で働く妹が会社の誇る家政夫をメイの家に派遣したことから物語が始まります。しかし、やってきたのは中年男性の家政夫・鴨野ナギサ(大森南朋さん)でした。優秀で予約のとれないスーパー家政夫とはいえ、中年男性に独身女性の部屋を片付けられることに最初は躊躇したメイでしたが、料理も掃除も完璧な上、仕事の疲れを癒してもらい励まされます。そうしているうちに彼の存在がなくてはならないものになっていきます。スーパー家政夫たるゆえんは、卓越した家事スキルもありますが、彼の信条に基づく利他意識と包容力といえます。これが通奏低音となり、さまざまな物事を順調に進展させる様子は、いまの時代に求められるマーケティング・ブランディングの勘所を示唆しています。
視聴者層のデュアルコア
 |
「多様な女性の生き方を認めたい」「働く女性を応援したい」という局側の思いが、結果として、一般視聴者とともに働く女性という2つの視聴者層(デュアルコア)をがっちりとつかみました。これは、昨今ビジネス界で脚光を浴びる、共通価値の創造(CSV:Creating Shared Value)に当てはまります。
あわせて、マーケティングの新しい潮流にも資するアプローチです。現代マーケティングの父と名高い、ノースウェスタン大学ケロッグスクールのフィリップ・コトラー教授は「マーケティング3.0」として、「企業と社会の両方に価値を生み出す事業活動」と提唱しています。企業はより大きなミッション・ビジョンを持って世界に貢献し、「社会の不安や課題に対するソリューション」を提供するというスタンスを構えなければならないと唱えています。企業は、生活者に製品・サービスだけでなく、精神的価値や社会的価値をも提供する存在へ変貌することが期待されています。
放送局として、数字(視聴率という経済的価値)の獲得だけでなく、働く女性へのエールやコロナ禍にストレスフリー(社会的価値)というデュアルコアを創出しています。綺麗になった部屋、おいしい手料理で豊かな気分になれるという姿が、ステイホームが叫ばれるコロナ禍の現状において、多くの共感が得られたこともあるでしょう。とりわけ、大森さん演じる家政夫・ナギサさんが作る「ナギごはん」は、料理家・栗原心平さんが監修を務めるとともにレシピを公開したことも、ウィズコロナ社会のニーズを捉えたともいえます。
ナギサさんは会社勤めをやめ、「お母さんになるのが夢だった」と語り、心を込めて完璧な家事をこなします。働く女性だけでなく、専業主婦など伝統的な「お母さん」の存在を再評価している点も、現代社会への大事なメッセージが込められています。
 |
こうした奥深さによって、火曜日・夜10時は働く女性を応援する枠として、視聴習慣のブランド化につながったのであれば、サステナブル・ブランディングのベストプラクティスといえましょう。
テレビ局関係者によれば、大ヒットするドラマは時代にマッチしているとのことです。当たったドラマは決まって時代との親和性が高いということは、ドラマ制作に限らず、「事業を通じた社会課題解決」が求められている全ての業種業態の企業に該当します。
「利他意識・包容力」は競争優位の源泉
おじさん家政夫のナギサさんは、完璧な家事の業務をこなしつつ、仕事で疲れ果てて帰宅したメイを内助の功のごとくサポートするとともに、仕事に対するさりげないアドバイスをくれる包容力あふれる人物です。その姿はまるでお母さんのようです。
ナギサさんがそうする理由は、彼が大手製薬会社のMRとして優秀な成績で活躍するビジネスパーソンであった時代に、お母さんのような包容力で部下を支えることができなかったことに後悔の念に駆られていたことです。そうした経験から、ナギサさんは家政夫の仕事を通して、人のために尽くすことを信条とし、社会のために貢献できることが、自分自身のやりがいにもつながるという利他意識と仕事観を持つようになります。
彼の利他意識と包容力が、家事というサービスを超えて、人と人の信頼関係を醸成し、頼りがいのある一目置かれる存在へと昇華させています。ついに顧客であるメイから「ナギサさんがいない生活なんて考えられない」「ナギサさんと一緒にいると心から安心するんです」とまで言わしめることになります。これは真のパートナーの姿といえ、営業パーソンとして目指す境地でしょう。良い商品・サービスの提供はもちろんですが、商品はともするとコモディティ化(品質での差別化が困難な状態)してしまいます。そこで決め手となるのは、商品スペックを超えて、「あなたを見込んで」「あなただからこそ」と言われることが醍醐味です。これが、企業ブランドの真骨頂です。
コロナ禍によってリモートワークが増え、営業手法や働き方など、既存のやり方では通用しにくい時代を迎えています。こういう時代だからこそ、自社(自分)の信念をしっかりと持ち、常に環境変化に適応できる能力を備えることが成否を分かちます。
自社の存在意義を明確にし、ならではの持ち味を発揮して、顧客や社会にとってなくてはならない存在であるための戦略メソッドが、サステナブル・ブランディングです。

細田 悦弘 (ほそだ・えつひろ)
公益社団法人 日本マーケティング協会 「サステナブル・ブランディング講座」 講師 一般社団法人日本能率協会 主任講師
1982年 中央大学法学部卒業後、キヤノン販売(現キヤノンマーケティングジャパン) 入社。営業からマーケティング部門を経て、宣伝部及びブランドマネジメントを担当後、CSR推進部長を経験。現在は、企業や教育・研修機関等での講演・講義と共に、企業ブランディングやサステナビリティ分野のコンサルティングに携わる。ブランドやサステナビリティに関する社内啓発活動や社内外でのセミナー講師の実績豊富。 聴き手の心に響く、楽しく奥深い「細田語録」を持ち味とし、理論や実践手法のわかりやすい解説・指導法に定評がある。 Sustainable Brands Japan(SB-J) コラムニスト、経営品質協議会認定セルフアセッサー、一般社団法人日本能率協会「新しい経営のあり方研究会」メンバー、土木学会「土木広報大賞」 選定委員。社内外のブランディング・CSR・サステナビリティのセミナー講師の実績多数。 ◎専門分野:サステナビリティ、ブランディング、コミュニケーション、メディア史 ◎著書 等: 「選ばれ続ける会社とは―サステナビリティ時代の企業ブランディング」(産業編集センター刊)、「企業ブランディングを実現するCSR」(産業編集センター刊)共著、公益社団法人日本監査役協会「月刊監査役」(2023年8月号) / 東洋経済・臨時増刊「CSR特集」(2008.2.20号)、一般社団法人日本能率協会「JMAマネジメント」(2013.10月号) / (2021.4月号)、環境会議「CSRコミュニケーション」(2010年秋号)、東洋経済・就職情報誌「GOTO」(2010年度版)、日経ブランディング(2006年12月号) 、 一般社団法人企業研究会「Business Research」(2019年7/8月号)、ウェブサイト「Sustainable Brands Japan」:連載コラム(2016.6~)など。















