 |
サステナブル・ブランド ジャパン(SB-J)は、法人会員コミュニティの2020年度プログラム初回となる「第1回SB-Japanフォーラム」を21日、博展(東京・中央)本社で開催した。フォーラムでは米サステナブル・ブランドが6月にオンライン開催した「SB 2020 Leadership Summit」の報告のほか、世界の最先端の潮流のひとつで今年度のSBグローバルテーマでもある「Regeneration(再生/再生可能性)」についての解説や、企業の影響力を最大限に発揮して持続可能な社会を目指すイニシアチブ「#BrandsforGood」の紹介が行われた。
今フォーラムは新型コロナウイルス感染症拡大への対応により、初めてオンラインを併用して開催した。
SB 2020 Leadership Summit報告
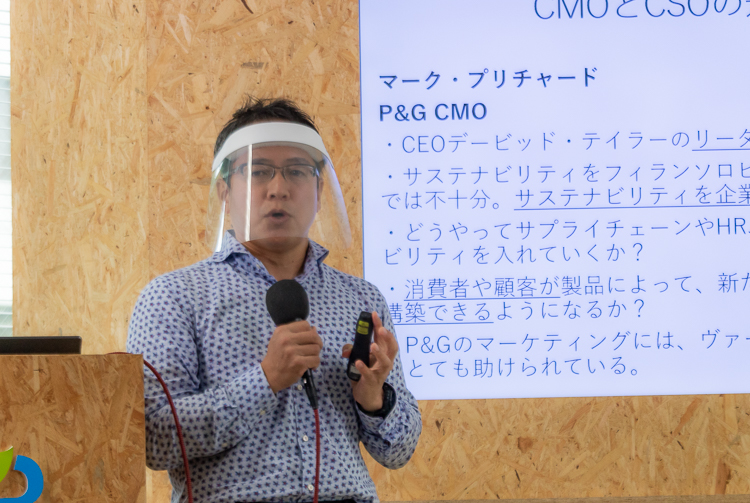 |
SB 2020 Leadership Summit は企業のCMO(マーケティング責任者)とCSO(サステナビリティ責任者)を中心にそうそうたる顔ぶれが参加し、2日間にわたり多数のセッションが開かれた。参加した青木茂樹・SBJアカデミックプロデューサーはその中から興味深いセッションをピックアップして紹介。同サミットでは「私たちの世界(社会)がどうなっているのか、どう修復するのか」「マーケティングとサステナビリティがどう連携をとるのか」といった多角的な視点から議論が深められた。
参考記事=
SB Leadership Summit 1日目: ポストコロナの社会とクライメイト・ポジティブな未来をどう築くか
SB Leadership Summit 2日目:困難な時代に、ブランドが成長しながら持続可能なカルチャーをつくりだすには
青木プロデューサーは参加を通し、ポイントを次のように挙げた。
・YOU&MEの世界観へ、コラボレーションのパラダイムの必要性
・従来の経済学からドーナツ経済学モデル(Doughnut Economic Model)へ
・バイオミミクリー(Biomimicry):ネットワーク構築や互恵性(相互性)を考慮する。
・多様性こそが回復力のある社会をつくる。
・サステナビリティを企業戦略に(Built in)。
・CMOとCSOの連携による力を生かす。
・クロスセクションの連携だけでは不十分。多様な個人の多様で異なるものの見方が重要だ。
リジェネレーションとは何か
続いて登壇した足立直樹・SB国際会議サステナビリティプロデューサーは「今、企業に求められるリジェネレーション」と題して事例をもとにリジェネレーションとは何かを解き明かした。
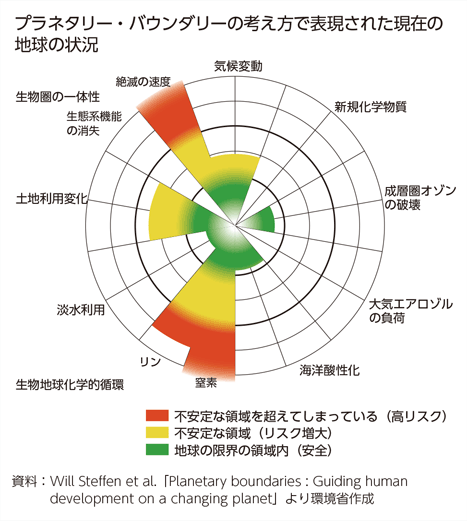 環境省「平成29年版環境白書」より引用
|
地球の限界(プラネタリー・バウンダリー)の研究において、人類の活動は気候変動などいくつかの項目ですでに閾値を超え、地球は危険な状態にあると指摘されている。人類はこれまで同様に環境負荷を減らすだけでなく、プラスの影響をつくっていかなければならない。それが「リジェネレーション(再生/再生可能性)」だと言われていると足立氏は解説する。
では、本当にそれは実行可能なのだろうか。持続可能性を実現しようとするとき、これまではエネルギー効率を見直すなどの方法で環境への負荷を下げる努力をしてきたが、「工業技術だけでは難しいのではないか」とも言われるという。生き物のシステムや、自然界のデザインにヒントがあるのではないかという観点から注目されているのが「バイオミミクリー」という考え方だ。
例えば、LIXILはカタツムリの殻の構造を模倣して汚れにくいタイルを開発した。森永乳業と東洋アルミニウム(大阪・大阪)は共同で、蓮の葉をヒントに撥水包装材を開発し、ヨーグルトの蓋などに採用している。
また、ファッション業界でも自然から学ぶ取り組みが進む。米バイオミミクリー・インスティチュートはレポート「The Nature of Fashion: Moving Towards a Regenerative System」を発表した。その中で、ファッション業界は既存の「つくり、使い、捨てる」というリニアのモデルから、植物性の繊維を利用する循環型モデルの構築へと転換が可能であることを示している。
 |
環境再生型農業に挑戦する大企業も現れている。足立氏は次のような具体的事例を紹介した。
・ゼネラル・ミルズ
米国の大手食品会社。2030年までに100万エーカーの農地で再生型農業を行うことを明かした。2019年に取り組みを始め、2025年までにバリューチェーン全体で排出CO2量を28%削減することを目標のひとつとしているが、1年間ですでに14%の排出量削減を実現しているという。
・ユニリーバ
2039年までに原料の調達から店頭販売までの過程で製品から生じる温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを目指すことをコミット。環境再生型農業への転換をサプライヤーに促し、今後10年間で環境ファンドへ10億ユーロの投資を行う。
・ケリング
グッチなどの高級アパレルブランドを束ねる仏ファッション大手。生物多様性を重要視する企業戦略を発表し、環境にポジティブなインパクトを与える再生型農業の促進を具体的にコミットした。
・パタゴニア プロビジョンズ
アウトドアメーカー、パタゴニアの食品部門。多年草穀物「カーンザ麦」を利用したビールなどを開発し、耕すことを最小限にした「環境再生型有機農業」を実行する。
足立氏は再生型農業のメリットを「環境にいい、農家にいい、企業にいい」と説明する。農家にとってもコストが減り収入が安定化し、省力化する場合もあり、レジリエンスを得ることができる。企業にとってはリスクマネジメントであるだけでなく、原料の安定供給を可能にするほか、ブランドがリーダーシップを発揮し顧客へのアピールにもなる。さらに農業だけでなくさまざまな分野でリジェネレーティブという言葉が見られるようになった。
国内の例として挙がったのは、小湊鐡道(千葉・市原)が2017年に行った「逆開発」だ。同社は養老渓谷駅の駅前のアスファルトの舗装をはがし、地面の一部を土に戻した。沿線の荒廃した竹林を菜の花畑に変え、ディーゼル機関車が速度を落として走る。「当時はまだそういう言葉はなかったが、日本流リジェネレーションと言えるのではないか」と足立氏は話す。
折しも新型コロナウイルスのパンデミックに直面し、今後の社会は大きく変わろうとしている。足立氏は「ペストの流行がルネサンスを生んだという見方もある」と話し、さらに米国の小説家、マーク・トウェインの次の言葉を紹介してこのセッションを締めくくった。
「歴史は同じようには繰り返さないが、韻を踏む。(The past does not repeat itself, but it rhymes.)」
#BrandsforGoodが変革を促す
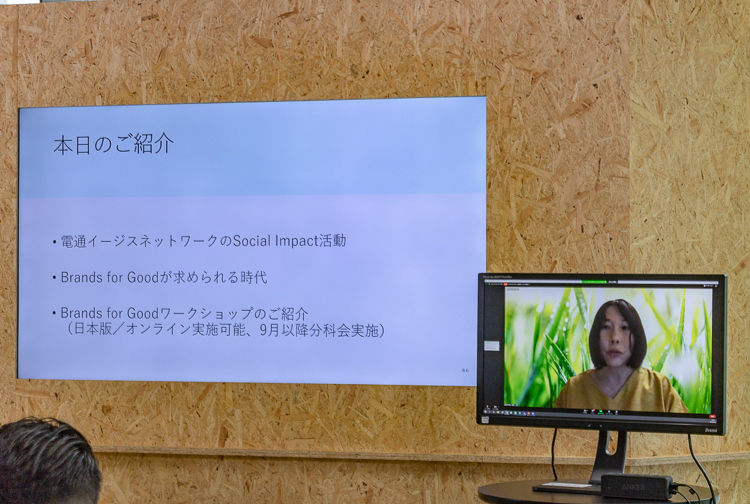 田中理絵氏はオンラインでの登壇
|
SB-Jフォーラムでは毎年、ひとつのテーマを連続で掘り下げる「分科会」を開催する。今年のテーマは「#BrandsforGood(以下、B4G)」だ。今回は分科会に先立ち、B4Gの紹介が行われた。
B4Gは米サステナブル・ブランドのコーポレートメンバーシップから生まれた、ブランドの影響力を最大限に活用し市場をけん引することで、消費動向や生産の動向を「持続可能性」へと導こうという意図のイニシアチブだ。P&Gやペプシコ、ナショナルジオグラフィックなど業界を問わず大手企業が参加する。その中に、英国に拠点を置く広告代理店、電通イージスネットワークが名を連ねる。
フォーラムでB4Gの概要を紹介したのは電通 グローバル・ビジネス・センターの田中理絵氏だ。同氏は「広告業界でもブランド、パーパス、サステナビリティがトレンドになっている。どこのセッションでもその言葉を聞かないことはない」と切り出した。
田中氏は「よく言われていることだが、10年前は広告、DMなどタッチポイントの2/3がブランド主導だったが、現在ではソーシャルメディアやレビュー、ブログなど消費者がつくる消費者主導に変化している」と解説する。それに伴い、マーケティングの成功は「消費者の行動変化」ではなく「ブランドの行動変化」となっている。
「サステナビリティの方向に世界が動くということは、すでに皆がわかっている。そして自分たちが今、目の前でできることもわかっている。ブランドに求められるのは短期と超長期の道筋をつなぐことだ」と話した。
そして、65%の人は購買行動によって企業・ブランドが良い行いを続けることに影響を与えられると思っているが、実際に環境や社会に良い(と表明している)商品やサービスを購入している人は28%に留まるという調査結果がある。この差は企業にとっては「伸びしろ」であるという点も無視できない。
このようにして始まったB4Gは、以下のようなビジョンを持っている。
・#BrandsforGoodは、持続可能な未来を築きながら、私たち全員がGood Lifeを生きることができると信じている。
・私たちは力を合わせ、気候変動を逆転させ、強靭な社会を構築し、健全な天然資源の利用を確立させるためのインパクトを与える活動を行う。
・私たちは、消費者がより持続可能な行動をとり、企業がサステナブルなソリューションを成功させることを支援する。
2018-2019年の1年間でビジョン、ミッション、バリューだけでなく影響領域と変化の道筋を定義し、ブランドのアクションを促すワークショップのためのツールキットを開発した。今後のSB-Jフォーラムの分科会では、全3回で参加者がこのワークショップを体験する予定だ。












