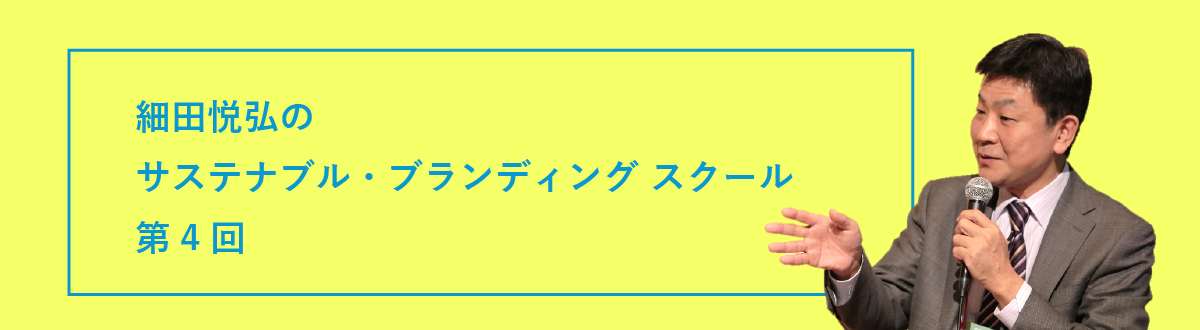 |
 |
どちらが勝っても、悲願の初優勝。第101回夏の甲子園・決勝戦。大一番にふさわしい素晴らしい試合でした。ただ、試合そのものにも感動しましたが、そこに至るプロセスや高校野球に対する向き合い方に心打たれた方も多かったでしょう。サステナビリティ時代の企業のあり方にも、貴重な示唆を与えてくれました。
目標は試合に勝つこと、目的は人間形成
 |
令和初となる夏の甲子園で念願の初優勝を果たしたのは、大阪代表・履正社高校でした。対戦チーム・星稜高校の注目の奥川投手は、日本一の履正社打線相手に粘り強く堂々と投げ、爽やかな感動をもたらしました。そこで、誰もが「あの人の感想を聞きたい」と思ったことでしょう。もちろん、星稜OBで巨人やヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏です。
彼のこんなコメントがすぐに飛び込んできました。
「林監督については、選抜大会以降大変だったと思う。ここまで来られたことは、素晴らしいですし、大きな財産になったと思います。でも、ここで優勝できないのが星稜。母校のそういうところも大好きです。何か新たな宿題が残った感じですね。また、あらためてチャレンジして全国制覇をねらってもらいたいですね」
「ただ目標は全国制覇かもしれませんが、星稜高校野球部のモットーは、あくまでも、野球を通しての人間形成です。それが校訓である『社会に役立つ人間の育成』につながっていくと考えています」
現代を生きる企業においても、収益は目標、目的は「社会の役に立つこと」という考え方は非常に大切です。この目的(存在意義:Purpose)を企業理念としてきちんと標榜し、それに基づく一貫性のある企業行動・広報活動が社会(ステークホルダー)のファンを生み出し、持続的成長・中長期の企業価値向上につながります。財務だけでなく、財務以外(非財務)も評価される時代です。
ここまでは、星稜高校を通じて、高校野球への向き合い方を紹介しました。次は、勝利へのプロセスの観点から、待望の初優勝を果たした履正社高校を取り上げます。こちらも、企業経営や広報(特にインナー)にとって示唆に富んでいます。
「教えすぎない教え」~岡田龍生監督の著書タイトル
「教えすぎ」は、選手の自主性を奪う。チームを日本一に導いた、履正社高校・岡田龍生監督のユニークな指導法が話題です。履正社を全国屈指の強豪校に育て、4人の高卒ドラ1も輩出した、名将の「自主性重視の指導法」です。選手たちの成長を促進するためには、何よりも選手自身が自主的に練習に取り組んでいくことが求められます。そのために、「教えすぎない」よう細心の注意を払いながら指導を続けてきました。
岡田監督の高校時代は完全なスパルタ方式で、本当に厳しく指導されたそうです。すべてにおいてやらされている野球で、監督の言うがままという状況でした。その後、やはり自分で考えながら、いろんなことを試行錯誤して取り組んでいくことが大事だという考えに至りました。選手にいろいろな情報やアドバイス、ヒントは与えるものの、選手自身がそれを自分でどう捉えて取り組んでいくのかが大切だということです。
従前の高校野球は、監督の言うことをいかに忠実に実践するかという「従う力」を身に付けることが重んじられてきましたが、いまの時代は自分で判断して自分の才能をどう開くかという「自主性」を尊重するスタンスが主流となっています。人が見ていようが見ていまいが、必要と思ったらやる。表裏のない、常に安定した気持ちで何事にも取り組む。そうすると、野球の結果もおのずと安定した結果が出てくるそうです。普段の生活は間違いなく野球のプレーにも表れるとのことです。この自主性を養う指導法が、見事に開花した初優勝でした。
上下関係の権力による指揮命令のみで人を動かそうとすれば、パワハラの温床となります。時代の価値観が変容する中で、持続可能ではありません。たとえ試合に勝っても、社会に負けることになります。人権重視の今日、スポーツ界もビジネス界も組織運営の勘所は共通のようです。
保護者もチームメイト。そして、ステークホルダー
 |
履正社は全寮制ではないこともあり、岡田監督は保護者とも細かく面談しています。選手たちの学校や練習の様子、普段の状況を伝えることで、お父さんお母さんの方も「そういう状況なのか」と理解できます。自分の指導方針や考え方を説明し、家庭でもそうした意向に沿って協力してほしいと申し入れます。丁寧に話をすることによって、保護者・指導者・選手たちが一体となって取り組むことができ、選手の力が一段と伸びるとのことです。監督は「親御さんもチームメイト」と明言しています。
これこそが野球部監督と家族とのエンゲージメントです。保護者も選手も「ステークホルダー」であり、指導者・選手・保護者の三者の信頼関係が高まれば、おのずとチームのパワーアップにつながります。企業とステークホルダーの関係も同様です。ステークホルダーとの関係の良し悪しは、企業の命運を左右します。
「CSRマインド」が自主性を生む
履正社の「自主性」、星稜の「人間形成」をゴールとする高校野球観…。
現代企業においても、社会の要請や期待に自主的・主体的に応えることが強く求められています。「社会への対応力」は企業経営の生命線となります。これがCSRの本質です。そのためには、社員一人ひとりが、CSR視点のモノの見方・考え方を身に付ける必要があります。これを「CSRマインド」といいます。このCSRマインドを社内で醸成することが、インナー広報の重点テーマとなっています。
 |
とかく個々のテーマ毎に無味乾燥に機械的に取り組み、やらされ感や横並び感が生じてしまいがちですが、社員一人ひとりが「CSRマインド」を備えることによって、その背景にある本質的な意味や意義を理解し、自主的・自発的に取り組む原動力となります。
社内啓発で重要なことは、知識偏重ではなく、本質的・体系的な理解を促すことです。基礎となる理論や原理原則を腹落ちしてもらえるよう努めることです。意味がわかれば、意義に気づきます。意義に気づけば、自主的・主体的に課題に取り組むようになります。
過去のことなら、前例を見ればいい。今だけのことなら、他社を見ればいい。中長期の発展を目指し、先(将来)に立ち向かうためには、自分の頭で考えることが決め手となります。
ここで、松井秀喜氏が高校時代の恩師・山下元監督から教わったとされる珠玉のフレーズを記しておきます。
心が変われば行動が変わる
行動が変われば習慣が変わる
習慣が変われば人格が変わる
人格が変われば運命が変わる
「社格・社柄・社徳」は企業競争力
社員のマインドが変われば、会社の未来(運命)が変わります。
令和の時代、個人としても「人格、人柄、人徳」が優れた人と付き合いたいとすれば、企業もまた、業績のみならず「社格・社柄・社徳」が、企業評価の新しいモノサシとなっています。企業も高校野球部も、実力だけでなく、時代と調和した感性を備え、「自校(自社)らしさ」を発揮することで、サステナブルなブランドとして輝き続けることができます。
☆編集部からお知らせです。
来月、細田さんの恒例の「CSRブランディング研修」が開催されます。サステナビリティ時代の企業ブランディングにご関心のある方は、以下より詳細をご覧下さい。
https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=22031

細田 悦弘 (ほそだ・えつひろ)
公益社団法人 日本マーケティング協会 「サステナブル・ブランディング講座」 講師 一般社団法人日本能率協会 主任講師
1982年 中央大学法学部卒業後、キヤノン販売(現キヤノンマーケティングジャパン) 入社。営業からマーケティング部門を経て、宣伝部及びブランドマネジメントを担当後、CSR推進部長を経験。現在は、企業や教育・研修機関等での講演・講義と共に、企業ブランディングやサステナビリティ分野のコンサルティングに携わる。ブランドやサステナビリティに関する社内啓発活動や社内外でのセミナー講師の実績豊富。 聴き手の心に響く、楽しく奥深い「細田語録」を持ち味とし、理論や実践手法のわかりやすい解説・指導法に定評がある。 Sustainable Brands Japan(SB-J) コラムニスト、経営品質協議会認定セルフアセッサー、一般社団法人日本能率協会「新しい経営のあり方研究会」メンバー、土木学会「土木広報大賞」 選定委員。社内外のブランディング・CSR・サステナビリティのセミナー講師の実績多数。 ◎専門分野:サステナビリティ、ブランディング、コミュニケーション、メディア史 ◎著書 等: 「選ばれ続ける会社とは―サステナビリティ時代の企業ブランディング」(産業編集センター刊)、「企業ブランディングを実現するCSR」(産業編集センター刊)共著、公益社団法人日本監査役協会「月刊監査役」(2023年8月号) / 東洋経済・臨時増刊「CSR特集」(2008.2.20号)、一般社団法人日本能率協会「JMAマネジメント」(2013.10月号) / (2021.4月号)、環境会議「CSRコミュニケーション」(2010年秋号)、東洋経済・就職情報誌「GOTO」(2010年度版)、日経ブランディング(2006年12月号) 、 一般社団法人企業研究会「Business Research」(2019年7/8月号)、ウェブサイト「Sustainable Brands Japan」:連載コラム(2016.6~)など。















