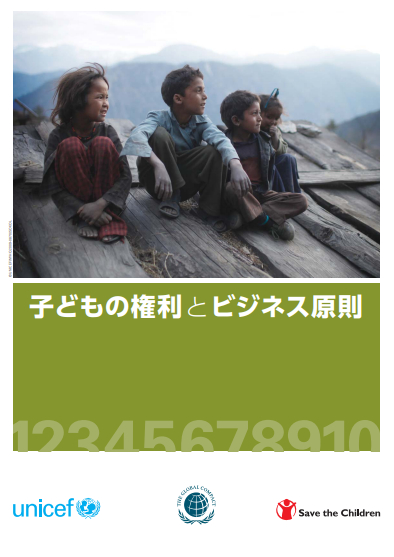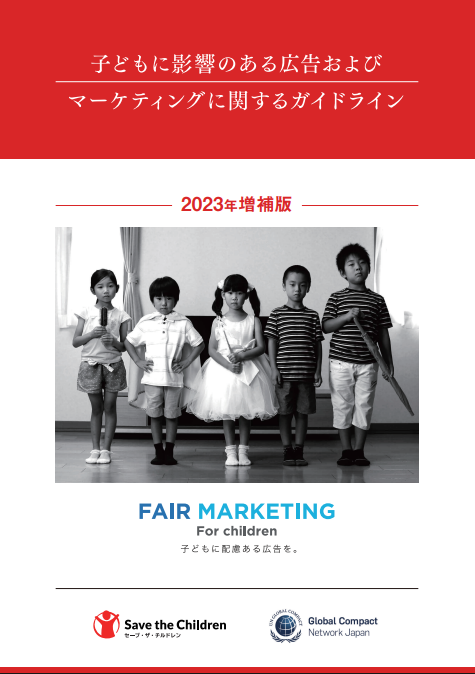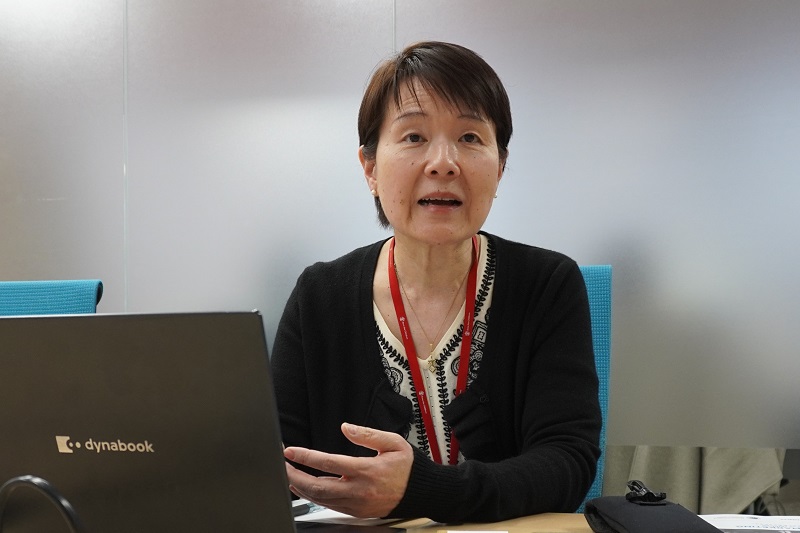
「ビジネスと人権」はもはや、企業が取り組まなくてはならないテーマのひとつとなっている。しかしその中で見落とされがちなのが「子どもの人権」だ。昨今では国内のエンタメ業界で若年者への性的虐待などが明るみになり大きな問題となった。またこれまで企業が取り組む子どもの人権とは、サプライチェーンの児童労働に視点が置かれていたが、本来企業は「子どもの権利(=人権)」をどのように考え、コミュニケーションを取るべきなのか? 来年設立40周年を迎える公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンで、長らく子どもの人権に携わってきた堀江由美子・アドボカシー部長に話を聞いた。(松島香織)
――「子どもの人権」を考えるにあたり、まずその基盤となるのが1989年に国連で採択された「子どもの権利条約」です。
堀江:この条約はセーブ・ザ・チルドレンの創設者エグランタイン・ジェブによる「子どもの権利宣言」の草案(1920年代)が基になっています。また同じ時代に「子どもの権利条約の精神的な父」と言われる、ポーランド出身で小児科医のヤヌシュ・コルチャックが「子どもは、だんだん人間になるのでなく、生まれながらにして既に人間である」と提唱し、子どもの権利条約の「子ども観」につながりました。
よく、人権は子どもを含む全ての人が対象なのに、なぜ「子どもの権利」が必要なのかと聞かれるのですが、子どもは成長や発達の途中にあるので、特別な権利で守られる必要があります。また、成長途中であっても、1人の人間として「権利の主体」だと周囲が認めることが必要です。
「子どもの権利条約」
1989年に国連で採択され、日本は1994年に批准した。54条あり、特に43~54条は国や組織が取り組むべき内容となっている。条約に批准した国は、批准してから2年後、そしてその後5年に一度、国連子どもの権利委員会の審査を受けることになっている。2019年の審査で日本は、特に緊急の措置を取るべき分野として「差別の禁止」「子どもの意見の尊重」「体罰」などが指摘された。
ビジネスが子どもに及ぼす影響は幅広い
――「ビジネスと人権」の取り組みの中では、「子どもの権利」をどのように捉えるべきなのでしょうか?
堀江:まず、「ビジネスと人権」の指針となっているのが、ハーバード大学のジョン・ラギー教授が提唱した「保護、尊重、救済」という枠組みです。これを基に2011年に国連「ビジネスと人権に関する指導原則」が作られました。ですが、この原則には子どもの権利の視点があまり入っていませんでした。
そこで、当時のセーブ・ザ・チルドレン・スウェーデンの事務局長が、グローバル・コンパクトとユニセフに声をかけて、この三者で2012年に作ったのが「子どもの権利とビジネス原則」です。
世界10カ国で600を超える企業、政府、市民社会と対話を実施し、また世界9カ国で約400人の子どもたちに、企業にどんな取り組みをしてほしいか、どういったことが課題であるかなどを聞き取りしました。それを基に作られたのが、この10の原則です。
「子どもの権利とビジネス原則 日本語版」
https://www.savechildren.or.jp/partnership/crbp/pdf/principles_01.pdf
1. 子どもの権利を尊重する責任を果たし、子どもの権利の推進にコミットする
2. すべての企業活動および取引関係において 児童労働 の撤廃に寄与する
3. 若年労働者、子どもの親や世話をする人々 に働きがいのある人間らしい仕事を提供する
4. すべての企業活動および施設等において、 子どもの保護と安全 を確保する
5. 製品とサービス の安全性を確保し、それらを通じて子どもの権利を推進するよう努める
6. 子どもの権利を尊重し、推進するような マーケティングや広告活動 を行う
7. 環境との関係および土地 の取得・利用において、子どもの権利を尊重し、推進する
8. 安全対策 において、子どもの権利を尊重し、推進する
9. 緊急事態 により影響を受けた子どもの保護を支援する
10. 子どもの権利の保護と実現に向けた 地域社会や政府の取り組み を補強する
堀江:「子どもの権利とビジネス原則」は、「ビジネスと人権に関する指導原則」以外にも、先ほどの「子どもの権利条約」や国際労働機関(ILO)の「最低年齢条約(138号)」「最悪の形態の児童労働条約(182号)」、また「国連グローバル・コンパクト」などもベースになっています。
ビジネスが子どもに対して及ぼす影響は、非常に幅広い。マイナスのインパクトを減らすとともに、企業はもっとプラスの行動も取れるはずです。
企業の方々は、子どもの権利とビジネスというと、原則2の児童労働について連想されることが多いですね。実際に非常に深刻な課題なのですが、例えば、全ての企業が関わる原則3も重要です。子どもの親や世話をする人へ、働きがいのある人間らしい仕事(ディーセントワーク)を提供することは、子どものウェルビーイングにもつながります。また、原則4はすべての企業活動において子どもを守り、子どもの安心・安全を確保することです。これはまさに昨今、子どもたちに対して直接的な性被害が及ぶという、エンタメ企業が問題になりましたが、あらゆる業界で子どもを守る取り組みが求められています。
――「子どもの権利とビジネス原則」は、天然資源の採掘から、製造、マーケティング・販売、消費者に至るまで、企業活動の幅広い領域に関わっています。
堀江:必ずしも子ども向け製品や食品を製造・販売している企業だけではなく、全ての企業が子どもとの何らかの接点を持っていることをまず認識していただきたいです。児童労働への対応から入る企業が多いのですが、それだけではなく、総務・人事でも関係はあるし、広告やマーケティング部門にも関係があります。
多くの企業では、CSR活動や社会貢献活動の一環として、子どもを支援したいと考えていらっしゃいますが、子どもへ負の影響をもたらしている分野があるかもしれない。そういう視点であらゆる企業活動の点検をすることが必要です。
子どもを「ステークホルダーの1人」だと意識する
――「子どもの権利とビジネス原則 日本語版」を2014年に出されて、10年経ちました。「子どもの権利」を取り巻く状況をどのようにお考えですか?
堀江:日本では2023年にこども家庭庁が発足し、こども基本法も施行されて、「子どもの権利」への取り組みはこれからというところ。残念ながら、企業に限らないですが、未だに子どもの権利に対する認知は低い状況です。
子どもの権利だけでなく「ビジネスと人権」全般に言えることかもしれませんが、サステナビリティ部門の方が経営層に理解を得たり、具体的な行動計画だったり方針に落とし込んでいくのに苦労されているというお話はよく聞きます。やはり経営層の意識を変えていくことはすごく重要ですし、課題だと思います。
企業は、子どもを「ステークホルダーの1人」だと意識しないと、いろいろなところでリスクは起こりうると思います。例えば原則6で示していますが、特にマーケティングに関しては、日本には規制がない状況です。広告を見て客観的な判断をすることが難しい低年齢の子どもたちに対して、刷り込みをしたり搾取するような活動は認められません。
マーケティング活動では「子どもの権利」をまず考えていただき、この年齢層に対して直接的なマーケティングをするのはやめておこうとか、あるいはむしろ「子どもの権利」への理解を高めるポジティブな影響を及ぼすようなコミュニケーションを取っていただくようにしてほしいですね。「子どもの権利」という視点で考えることで、企業活動・企業行動が変わってくるはずです。
今や企業は、投資家から「ビジネスと人権」に取り組むことを求められるようになっています。何よりも子どもは、どの企業にとっても未来の顧客であり、あるいは従業員であり、非常に重要なステークホルダーです。「子どもの権利」を尊重することは、長い目で見るとその企業の持続可能性にもつながります。
――マーケティングに関しては、「子どもに影響のある広告およびマーケティングに関するガイドライン」も発行されていますね。
堀江:2014年に「子どもの権利とビジネス原則 日本語版」を公開しましたが、なかなか企業の具体的な取り組みにつながっていないという課題意識から、この10の原則の中で、何を具体的に取り組んだらいいだろうと考えました。それで着目したのが、原則6「子どもの権利を尊重し推進するマーケティングと広告活動」です。ガイドラインには法的な拘束力も強制力もないですが、日本は先ほど申したように特に規制がないため、各企業の指針になるように策定し、2016年に発表しました。
実は、18歳未満の全ての子どもを対象とすることにこだわりました。子どもに対するマーケティングを注意して行っている企業でも、12歳以上など年齢を区切ってOKにしているところもある。ですが、特にインターネット広告では、あらゆる年齢で意図せず課金扱いになったり個人情報が悪用されたり、被害が出ています。こうしたインターネット上の広告・マーケティングを取り巻く課題が急速に増えたことを踏まえ、留意点などを追記した「子どもに影響のある広告およびマーケティングに関するガイドライン 2023年増補版」を発行しました。
――昨年、オーストラリアが16歳未満の子どもたちによるソーシャルメディアの利用を禁止するという発表がありました。何かお考えになることはありましたか。
堀江:インターネット、特にSNSを通じての被害は非常に増えていますし、実際ヘイトクライムやフェイクニュースなど、子どもたちは負の影響を受けています。しかし、デジタル空間へのアクセスは、子どもたちにとって必要な情報を得たり、他者とつながる機会でもあります。この件に関しては、セーブ・ザ・チルドレン・オーストラリアも反対のコメントを出しています。
一概に禁止すればいいというものではなく、インターネットのリスクや安全な利用に関するリテラシーを上げること。子どもが被害に遭わないように、プラットフォームや広告を出す企業や政府がしっかり対応するべきものです。
まずは企業が「子どもの権利」を尊重して、子どもを守り、子どもを搾取しない、子どもを利用しない。そういう意識が必要です。企業が自らのビジネスにおける子どもとの関わりを洗い出すことから始めていただきたい。その際にはぜひ「子どもの権利とビジネス原則」をガイドラインとして活用いただきたいと思います。
松島 香織 (まつしま・かおり)
サステナブルブランド・ジャパン デスク 記者、編集担当。
アパレルメーカー(販売企画)、建設コンサルタント(河川事業)、自動車メーカー(CSR部署)、精密機器メーカー(IR/広報部署)等を経て、現職。