サステナブル・ブランド ジャパン編集局
 |
サステナブル・ブランド ジャパンが主催する、サステナビリティに関する国内最大級のカンファレンス、「サステナブル・ブランド国際会議」(次回は「第9回サステナブル・ブランド国際会議2025 東京・丸の内」を2025年3月に開催)。ここでは毎年、「SB Student Ambassador」として全国から集まった高校生が、それぞれの地域の課題を踏まえた独自の解決策を発表する場がある。
出場するには学校ごとに論文を提出し、選考に残る必要があるが、その事前学習会となる「SB Student Ambassador ブロック大会」が今年も9月下旬から全国9会場で行われた。高校生たちはサステナビリティに取り組む起業家や、地域の企業のどんなアイデアをインプットし、そこからそれぞれの感性を生かしたどんなソリューションを考えたのか――。トップバッターの「中国ブロック大会」の様子から紹介する。(市岡光子)
東広島市長と広島大学学長が高校生にエール
 髙垣廣徳・東広島市長 ※
|
「中国ブロック大会」は9月28日に広島大学東広島キャンパスで開催され、中国地方5県から21校、148人の高校生が参加。プログラムは「午前の部」と「午後の部」の二部制で、午前の部では大会関係者による開会の挨拶と基調講演、午後の部では参加企業によるパネルセッションが行われた。
開会の挨拶では、東広島市長の髙垣廣徳氏※が登壇。同市の歴史とSDGsに関する取り組みを紹介した後、「地球上の一人ひとりがウェルビーイングを感じられる社会をつくること。そうした『SDGsの最終目標』に到達するためにも、若い力が必要だ。今回のイベントが皆さんの成長にとって有意義な場になれば」と、高校生たちにエールを送った。
また、会場となった広島大学の越智光夫学長は「本大会はZ世代の価値観や社会に求めるものを企業に発信できる場となる。参加者にとって実り多き1日となることを願っている」とVTRでメッセージを寄せた。
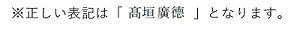 |
■基調講演 山内萌斗・Gab代表取締役CEO
「小さく近い」アプローチで社会課題解決を目指す
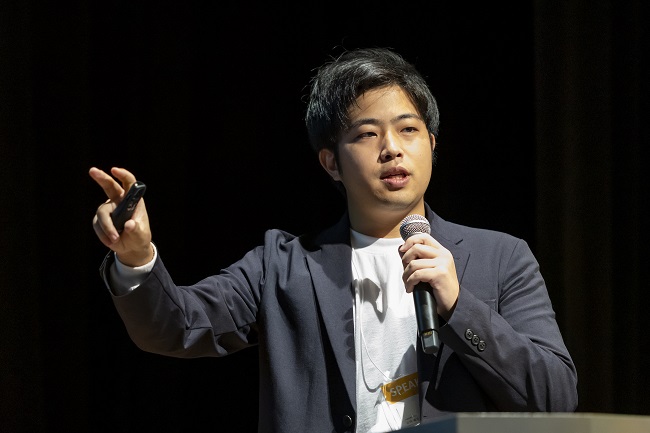 山内萌斗氏
|
基調講演には、Gab代表取締役CEOである山内萌斗氏が登壇した。Gabは、「社会課題解決のハードルを極限まで下げる」をミッションに掲げ、2019年12月に創業したスタートアップだ。現在、エシカルブランドに特化した商品販売・グロース支援プラットフォーム「エシカルな暮らし」や、ゲーム感覚でゴミ拾いを行うイベント「清走中」など、ユニークな発想で企画・開発された事業を展開し、収益化が難しいとされるソーシャルスタートアップの中でも順調に業績を伸ばしている。
こうした事業を展開する背景について、山内氏は、「気候変動や貧困、海洋ゴミ問題などの世界的な課題が日本では多くの人にとって身近に感じられず具体的な行動に結びつきにくい」と指摘。「日本は豊かで社会問題を実感しにくい国だからこそ、課題を日常の行動に置き換えることが重要だ」と語った。
さらに、廃棄リンゴから作られたかばんや海洋プラスチックを使ったアクセサリーなどを例に挙げ、「生活者が“心ときめく商品”を購入することで自動的に社会課題の解決につながるよう、そうした仕組みを作ることが大切だ」と力を込めた。
■地域とともに持続可能な社会を目指す――イズミ
ゲーム性を取り入れたリサイクル回収の仕組みづくりを
 |
午後の部では、4つの教室に分かれ、参加企業4社の講演を聴講。その後、参加企業から提示されたテーマに従って、「企業にどんなことをして欲しいか、また自分たちは何ができるか」をグループごとにディスカッションし、意見発表を行った。
 松永純一氏
|
広島市に本社を置き、中四国・九州地方を中心に総合スーパーストアを展開するイズミからは、サステナビリティ推進課の松永純一課長が登壇した。同社では、食品ロスやプラスチックの削減、省エネ・創エネの推進など多岐にわたる活動を進めているが、その中でもとりわけ「地域社会への貢献活動」が際立つ。地域で生産された食品の取り扱いによって、地域経済活性化と輸送時のCO2削減に貢献しているほか、「zehi」という独自総菜ブランドを通じ、販売点数に応じて地域の子ども食堂へ寄付している。
さらに、農業高校の生徒と連携し、サステナブル商品の開発にも取り組んでおり、これらの活動は地域社会で好評を得ているという。松永氏はその上で、「イズミのお客さまや地域の方々とともに、社会課題の解決に向けて何ができるのかを一緒に考えてもらいたい」と高校生たちに呼びかけた。
それを受け、高校生たちは、SDGsの認知度向上や地産地消の推進を目的とした店内イベントの開催、食品ロス削減の啓発を目的とした料理教室の実施、ゲーム性を取り入れたリサイクル回収の仕組み構築などを提案。地域に根ざした「スーパーストア」という場で、社会課題の解決に向けた多様な可能性を見出す機会となった。
■食品トレーのリサイクルでSDGsに取り組む、エフピコ方式の資源循環型リサイクル
地域の身近な施設に、回収ボックス設置を
 |
広島県福山市に本社を置く業界最大手の食品容器メーカー、エフピコのサステナビリティ推進室ジェネラルマネジャー・冨樫英治氏は、同社の資源循環型リサイクル「エフピコモデル」を紹介。同社は1990年から全国約1万8000拠点でトレーの自主回収を実施しており、リサイクルを事業の一環として実施している。取り組みの中では、新しい製品の運送と共に使用済みトレーを回収してリサイクル工場へ運ぶ仕組みを構築し、CO2排出削減にも成功。「水平リサイクル」により使用済みトレーを再び食品容器として再利用している。
 冨樫英治氏
|
講演では、プラスチック容器がすでに社会に欠かせないものであることから、自然環境を守りつつ便利な暮らしを維持する難しさについても触れられた。冨樫氏は「海洋プラスチック問題は、国や地域を越えて、世界全体が同じ目標に向かって協力し合うことが不可欠」と述べ、国際連携の重要性を強調。バイオプラスチックなど、石油由来ではない代替プラスチックの限界についても言及し、高校生にとっては問題の複雑さを考えさせられる機会となった。
「食品トレーのリサイクル促進」をテーマに行った高校生のディスカッションでは、具体的な提案が数多く寄せられた。あるチームは、足腰の弱い高齢者がスーパーの回収ボックスまで行くのが困難である点に着目し、地域の公民館など身近な施設に回収拠点を設置するアイデアを提示。また、フィルムをはがすことで、裏に描かれたイラストを楽しみつつ洗浄せずにリサイクルできるトレーや、子どもが自発的に回収したくなるゲーム機能付きの回収ボックスなど、生活者が自主的にリサイクルに参加したくなる仕組みが提案された。
■クルマを通じた地域課題解決への貢献とは――マツダ
インセンティブのあるライドシェアリングなどで、地域との絆を深める
 |
マツダ(広島県安芸郡府中町)は、SDGsの17の目標に基づき8つの重点テーマを定め、その解決に向けて取り組みを進めている。ESGコミュニケーショングループマネージャーの馬渡信行氏は、その中でも「地球」「人」「社会」の課題に焦点を当て、具体的な活動を紹介した。
 馬渡信行氏
|
地球規模では、2050年までにサプライチェーン全体でカーボンニュートラルの達成を目指し、2035年には世界の自社工場での達成を計画。塗装工程の効率化や再生可能エネルギーの導入などを推進している。また、地域のニーズに応じた電気自動車とエンジン車の活用や、広島大学と植物由来燃料の研究も進める。
「人」にまつわる課題については、身体の不自由な人も快適に運転できる車両の開発や、幅広い世代が車の魅力を体験できる「eモータースポーツ大会」を実施。「社会」では、広島県三次市で地域交通の改善の実証実験などを行っている。
これらの取り組みについて、馬渡氏は「社会の変化に対応し、社会貢献と企業の持続的成長を目指すことが重要」と述べ、マツダの未来の自動車像を結集させたコンセプトカーを画像とともに紹介。「車は人々の力となり、新たな出会いや活力を生む」とし、地域との協力で持続可能な未来を築きたいと強調した。
ディスカッションでは、地方の移動手段不足や高齢者の健康寿命延伸をテーマにした提案が多く出され、特定の地域内で運行するカーボンニュートラル燃料のバスや、移動と筋力トレーニングを両立する「サイクリングカー」、運転者にインセンティブを与えるライドシェアリングなど、環境に配慮しつつ地域の絆を深めるアイデアが出された。
■環境を守る家づくりとは?――YKK AP
緑やテクノロジーの活用で、家庭からサステナビリティの実現を目指す
 |
広島市に支社を置くYKK AP サステナビリティ推進部部長の三浦俊介氏は「窓から考えるサステナビリティ」をテーマに、窓の断熱性能向上の重要性を説いた。日本の家庭では、夏の外気熱の75%、冬の外気熱の50%が窓から室内に伝わるため、窓の断熱性強化がエネルギー消費削減や健康リスクの低減に効果的だという。
 三浦俊介氏
|
三浦氏は、欧米で主流の断熱性能の高い樹脂窓は、日本では10~15%の普及にとどまることなどを話し、高断熱窓の普及でカーボンニュートラルに貢献する方針を説明した。また、「日本は発電用の化石燃料を外国から高額で輸入しているが、リフォームで断熱性を高めれば、CO2削減と社会全体のコスト削減が可能だ。その分を地域経済に活用できる。家屋の断熱性向上は投資として積極的に取り組むべき」と力説した。
三浦氏の話を受けて、多くの高校生たちが、都市部でも自然の豊かさを感じられる環境づくりを提案。グリーンカーテンや観葉植物など緑を取り入れることで、都市部のヒートアイランド現象の抑制や住環境の改善を促すアイデアが出された。さらに、スマートフォンと連動した家電制御システムを活用し、住人が外出すると自動的に電力がオフになるシステムの導入などで、家庭内の消費エネルギーを抑える提案も。都市環境と住環境の両面から、持続可能な未来への道筋を描いた。
直感的かつ誰もが共感できるアイデアで、非常に魅力的
最後に、各企業のワークショップに参加したチームの中から4チームが代表発表を行った。
最初に発表したのは、イズミの講演に参加したチームだ。彼らは「めっちゃもりもりエコマーケット」と題し、広島の特産品を活用した地域活性化と、リサイクル素材を使用した商品展開、売れ残った商品の飼料化、小売企業間の連携による業界全体でのフードロス削減などを提案した。障がい者雇用も組み込み、収益を上げつつ社会課題の解決を目指す持続可能なビジネスモデルが評価され、イズミの松永氏から「収益モデルの構築と社会貢献を両立させた点が素晴らしい」との講評を受けた。
次に登壇したのは、エフピコの講演に参加したチームだ。彼らは「おみピコ」と名付けた子ども向けリサイクルボックスを発表。回収箱におみくじ機能を搭載することで、子どもをきっかけに家庭全体で自ずとリサイクルに参加できる仕組みだ。エフピコの冨樫氏は「リサイクル率向上の鍵は、トレー回収ボックスを設置しているスーパーへの来店率を上げること。今回の提案は来店頻度を高める可能性を感じられた」とコメントした。
続いて、マツダの講演を聞いた高校生たちからは、空飛ぶ車「CX AIR」が提案された。この車は、車内に搭載されたペダルをこいで蓄電し、渋滞時や緊急時にはその電気でプロペラを動かし、飛行できる仕組みだという。ペダルをこいで蓄電することで、CO2削減や運動不足の解消にも貢献するという。マツダの馬渡氏は「健康、街づくり、気候変動といった複数の課題を1つの解決策にまとめた点が印象的」と高く評価した。
最後に、YKK APへの提案を行ったチームは「緑を活用した街づくり」をテーマに、都市部のビルや住宅にグリーンカーテンや観賞植物を設置し、都市の環境改善と住民の健康促進を目指すアイデアを発表した。YKK APの担当者は「理想の街を明確に描き、論理的にアイデアを組み立てていた点が素晴らしかった」と評価した。
全体講評では、Gabの山内氏が「各チームの提案は直感的かつ誰もが共感できるアイデアで、非常に魅力的だった。今回の大会を通じて、皆さんが夢を叶えるうえで必要なヒントが得られたのではないか」とまとめ、参加者たちをたたえた。

SB Student Ambassador
「SB Student Ambassadorプログラム」とは、SB国際会議に参加し、高校生の立場から意見を発表するプログラムです。










