サステナブル・ブランド ジャパン編集局
 |
全国の高校生が持続可能な社会の在り方について議論し、アイデアを発表する「第5回 SB Student Ambassador ブロック大会」。全国9会場で開催されるうち、東北大会は10月5日に東北工業大学八木山キャンパス(仙台市)で開催され、計16校から100人の高校生が参加した。サステナブル・ブランド ジャパンのユースコミュニティ「nest」のメンバーによるファシリテーションのもと、高校生ならではの視点から、未来につながるアイデアを活発に出し合った。(横田伸治)
「挑戦することの楽しさと価値を感じて」SAの先輩たちからエール
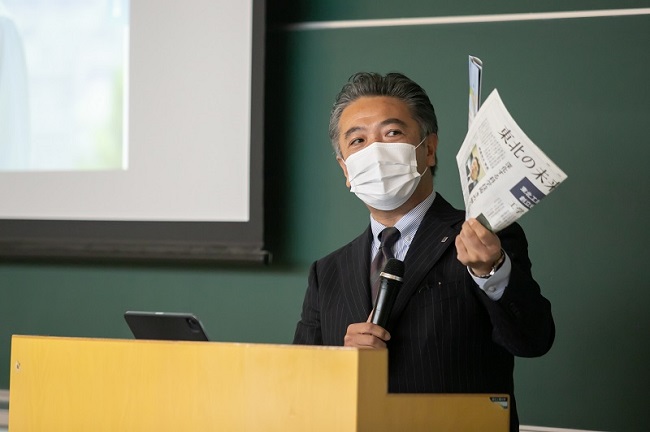 渡邉浩文 学長
|
東北大会の幕開けにあたり、会場となった東北工業大学の渡邉浩文学長は「工業大学である本学は、遠い先人たちの知見を蓄積しながら、これからの世の中の基盤づくりに取り組んでいます。皆さんにとっても、今日一日が実りある時間であることを願っています」と挨拶した。
続いて、昨年第4回の東北大会に参加し、ビジネスアイデア コンテストなどでも活躍する東北高等学校の伊藤海音さんと佐藤唯夏さんは「私たちも最初は『何となく面白そう』と考えて参加したが、SB Student Ambassadorで出会った仲間と、真剣に話し合って考えを伝えあうことが楽しくて、自分たち自身でSDGsのイベントを実施することにもなった。皆さんもぜひ、挑戦することの楽しさと価値を感じてほしい」と今年度の参加者たちにエールを送った。
■基調講演 香川 幹・一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン
水産業を“カッコいい”職業に、地域ぐるみで活動
 香川 幹氏
|
最初に基調講演を務めたのは、一般社団法人フィッシャーマン・ジャパンの広報・広告担当で潜水士の香川 幹(たかし)氏だ。同法人は、漁師の担い手不足や水産資源の危機、また日本人の魚食消費減少などの社会課題を背景に、宮城県石巻市の漁師が声を上げ、活動をスタートさせた。
「水産業をカッコよくて、稼げて、革新的な、新3K産業に」を掲げ、担い手育成事業や漁業体験プログラムの開発、県外から訪れる担い手候補者のための宿泊・交流施設の整備、さらに海産物の国外PRや、漁場の海藻が減る「磯焼け」の一因とされるウニの適正管理や海藻の移植活動など、サステナブルな地域漁業を実現するための事業を幅広く手掛ける。
香川氏は「最初は理解されなかった活動も、続けていくことで、次第に(地域の理解が)広がった。現在は地域ぐるみで活動できて全国にも広がっているので、皆さんにもぜひ、水産業の魅力を感じてもらえれば嬉しい」と呼びかけた。
■基調講演 関 芳実・StockBase 代表取締役
SDGsの知識だけではイノベーションは起こせない
 関 芳実氏
|
続いて、賞味期限などを理由に廃棄される防災用備蓄食品について、寄付元・寄付先をマッチングするプラットフォームを展開するStockBaseの関 芳実(せき よしみ)・代表取締役が登壇し「私はすごくもないし、特別でもない、普通の大学生でした」と話した。関氏は学生時代に偶然、企業が取引先に配布する営業用カレンダーが大量に廃棄されている現状と、高齢者施設で紙のカレンダーの需要が高いことを知り、マッチングの可能性に気づいた。その経験から、食品ロス削減を目指す現在の事業へとつながったという。
関氏は自身の体験をもとに、「SDGsの知識だけではイノベーションは起こせない。社会を変えるには、実践しかありません。矛盾に敏感になり、いろんな場所に行っていろんな人に会ってください」と語った。
■若者が残りたいと思える東北にするためには?――七十七銀行
キャラクターを活用して公共交通機関を元気に
 |
高校生が関心のあるテーマを選んで参加するテーマ別ワークショップには、七十七銀行、福島民報社、マイナビ宮城支社が登壇し、それぞれサステナビリティに関する取り組みを紹介した。高校生たちは、企業の講演のヒントをもとに、テーマに沿って90分間のグループディスカッションを行い、独自のアイデアを発表した。
 髙久智広氏
|
七十七銀行総合企画部企画課兼サステナビリティ推進室の髙久智広氏はまず、同社が東北地方の人口減少、未婚者増加、若者の東京圏への流出といった社会課題に取り組んでいることを紹介した。同社は、セミナーやファンド、助成金などを運営する「創業・新規事業支援」、地域企業の販路開拓や海外ビジネス支援、事業承継支援などを行う「地域中核企業支援」のほか、結婚相談所の開業や仙台市の再開発プロジェクトへの参画など、多様な事業を展開している。髙久氏は「企業は利益だけを出せば良いものではなく、社会的な責任を果たしていかなければいけない」と地域課題に取り組む理由を説明した。
高校生たちは6グループに分かれ、「地域に若年層が定着し、人口流出に歯止めをかけるためには、どのような取り組みをすればよいか?」をテーマに、アイデアを検討。その後、「首都圏の企業に務めつつ地方に定住できるよう、交通費を援助する」「公共交通機関がキャラクターとコラボすることで経営状況を改善し、電車やバスの本数を増やすと同時に地域経済も活性化する」といった案が発表された。
■SDGsを親しみやすく伝える高校生ならではのアイデアとは?――福島民報社
高校生の体験を小中学生に伝えていくような、教育の循環づくりを
 |
福島民報社は、地域企業や団体、県などとともに推進する「ふくしまSDGsプロジェクト」を紹介した。若者世代にSDGsを身近に感じてもらうため、地域の小中高校などに出張授業を行うほか、今年8月には「ふくしまSDGs博」を開催した。
 宗像恒成氏
|
福島民報社は、地域企業や団体、県などとともに推進する「ふくしまSDGsプロジェクト」を紹介した。若者世代にSDGsを身近に感じてもらうため、地域の小中高校などに出張授業を行うほか、今年8月には「ふくしまSDGs博」を開催した。同社広告局営業部の宗像恒成氏は「楽しんでもらいながら、『結果的にSDGsにつながっていた』ようなイベントにしたかった」と語るように、芸能人によるトークショーやクイズ、地域の高校生が企画・運営した子ども向けのSDGs体験ブースなどを実施した。宗像氏は「ただイベントでブースを出してもSDGsは広がらない。各出展者の活動をよりソフトに分かりやすく伝えられることが重要」と強調した。
ディスカッションのテーマは「学生が地元に関心を抱き、地域づくりに関心を寄せるには」。高校生たちは、6グループに分かれて議論を開始。「東北の学生が集まり、合同でお祭りを開催する」といったイベント実施に関する意見が多く出た一方、「高校生が地域の職業を体験し、感じたことを小中学生に伝えていくような循環を作ること」など、学校教育に示唆を与えるような発表もあった。
■人口減少を食い止める、地方でのキャリア形成とは――マイナビ
仕事だけでなく、暮らすことや住むこととセットで提案を
 |
マイナビ宮城支社の小池正徳・支社長は、「東京圏への流出を食い止めるためには、若者の東北地方におけるキャリア形成が重要」と述べ、東北地域の人口減少の現状と背景を、大学生世代へのアンケート結果を交えながら解説した。
 小池正徳氏
|
全国平均以上に高齢化率が高まっている背景には「県外への大学進学率・就職率が極めて高い」(小池氏)ことが挙げられ、Uターン就職が選ばれにくいいちばんの理由としては、「志望する企業がない」が挙げられたという。小池氏は「地元を出てしまった後は、地元の企業を知る機会がない。もっと早いタイミングで知ってもらう方法を考えたいし、就職したいと思われる企業ももっと増やしたい」と語った。
小池氏の講演を踏まえ、高校生は「未来の地元・東北で『はたらく』こと」をテーマに議論に臨んだ。グループワークでは、「自分たちは東北に残りたいと感じているか?」などと本音で話し合う場面も。その上で、「仕事だけでなく、暮らすことや住むこととセットで考えるべき。求人サイトにも、地域の文化や特徴的な政策を掲載する」「県外の大学に進学した後、Uターン就職すると生活支援などの特典を受けられるようにする」などといったアイデアが飛び出した。
「当たり前」を無くして、これからも考え続けて
最後は、参加者全員が講堂に集まり、3テーマの代表チームがそれぞれアイデアを発表した。
七十七銀行が提示した、地域活性化に向けた若年層の定着について、どのような取り組みができるかを考えたチームは、「東北各県を越境する、イベントや店舗運営の企業を創設する」というアイデアを出した。「都心にもあるショッピングセンターを地方に作っても、後追いに過ぎない。特産品や伝統行事を生かし、地方ならではの良さを出さないといけない」「企業を作ることで、地域に関心のある若年層の働き口になり、経済循環も生める」といった意見を発表し、そうした視点が評価された。
福島民報社のプログラムに参加したチームは、若者が地域に関心を持ち地域づくりを考えるためのアイデアを考えた。高校生たちはまず、「関心を持つだけでなく、誇りにつながることが重要」と課題を整理したうえで、「地域イベントや学校教育、SNSでの発信などを組み合わせるべき」と発表した。
マイナビの講演から「東北で働くこと」を考えたチームは、全国の中高生を東北地方に招き、魅力や文化を感じてもらう体験ツアーを提案。普段関わらない地域の友人ができたり、学校ではできない体験をしたりすることで、東北地域に思い出を作ってもらい、深い関係人口とできるというアイデアだ。
各プログラムの発表を聞いたStockBaseの関氏は、「皆さんが“サステナビリティ”という言葉を口にすることが、持続可能な社会について考えているという意思表示になります。一方で、(サステナビリティや)SDGsという言葉も古くなっていくもの。『当たり前』を無くして、これからも考え続けてほしい」と呼びかけた。

SB Student Ambassador
「SB Student Ambassadorプログラム」とは、SB国際会議に参加し、高校生の立場から意見を発表するプログラムです。










