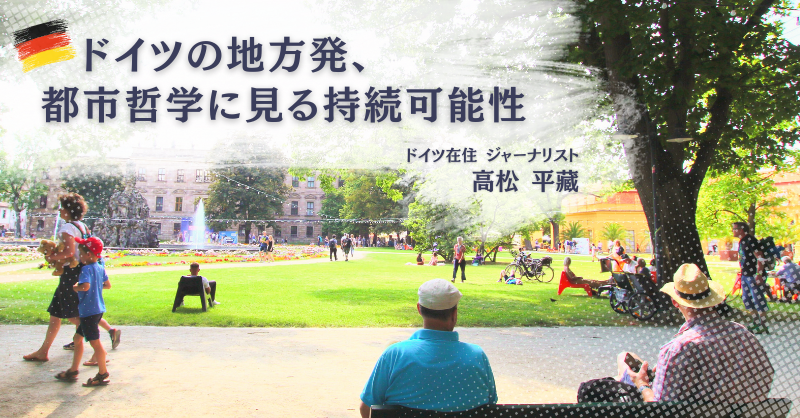 |
ドイツのクリスマスマーケットは、単なる観光名所ではなく、地域社会の文化やアイデンティティーを反映する重要な場である。筆者が暮らすエアランゲン市(人口約12万人)のクリスマスマーケットを見ながら、その真価を考えたい。
■小さな町でも開催されるクリスマスマーケット
ドイツでは、約3000ものクリスマスマーケットが開催されている。しかし、日本の観光ガイドに掲載されるようなところはごく一部で、その多くは各自治体で行われている。小さな街だと、12月のある週末にだけ行われるようなところもある。
エアランゲン市での開催は、今年は11月25日から12月24日まで、中心市街地で開催される。マーケットでは、木製の小屋が立ち並び、キラキラと輝く電飾とモミの枝が装飾され、グリューワインや焼きアーモンドの香りが漂う。訪れる人々は、手作りの工芸品などを手に入れながら、冬のおとぎ話のような雰囲気に浸ることができる。
 クリスマスマーケットは楽しみや余暇をすごく空間だが、地域の社会的資本を強くすることにつながっている(筆者撮影)
|
クリスマスマーケットは小規模事業者や生産者にとって重要な収入源となっており、地域経済も潤す。それと同時に注目すべきは、これらの市場が地域社会の人々の関係を深める役割を果たしている点だ。友人と誘い合い、家族が楽しみで訪ねる。スポーツや文化、ボランティア、経済関係などの仲間同士が集まることもある。遠方からお客さんが来ると、案内することにもなる。
つまり、無数の社交の場になっているのだ。これがドイツのクリスマスマーケットが持つ「社会的価値」であり、観光資源としてだけではない意義である。
■中心市街地が開催場所であるその意義
クリスマスマーケットの社会的価値を高めているのは、「開催地」が中心市街地であることも見なければならない。中心市街地はその自治体の伝統的な建物や広場が残され、歩行者専用ゾーンとして整備されていることも多い。また多くの樹木やベンチが配置されている。普段から「滞在の質」を高めることに注力された「都市社会のリビングルーム」なのだ。とりわけクリスマスマーケットは「クリスマス仕様のリビングルーム」に変わるかたちだ。
その価値が確認されたのが新型コロナウイルス流行時だった。2020年は、オンラインイベントなどを代替的に試みたところもあったが、感覚的な体験を再現することが難しく、多くの人々が求める「実体験」が欠落した年だった。
またエアランゲン市を見ると、ユダヤ教の希望と平和を願う気持ちが表現されるハヌカ祭の燭台点灯式も中心市街地で行われる。これは地域社会の多様性を象徴する機会であり、市民が互いの文化を尊重し合う機会になる。特に近年、反ユダヤ主義や外国人排斥の主張が台頭するなど、社会的緊張が高まっている。それに対して同市は、共生社会を目指す姿勢を示しているかたちだ。燭台点灯式には、関心のある市民や地域のリーダーが参加し、音楽が演奏され、祝福の言葉が交わされる。
他方、日本の大都市で開催されるクリスマスマーケットを訪ねたドイツの若者からこんな話も聞いたことがある。本場さながらの雰囲気を感じつつも「何かが違う」と感じた。その理由は、ドイツのように、歴史的な景観の中で開催されているわけではなかったことだ。クリスマスマーケットは都市の歴史的コンテクストや⽂化的背景の中で⾏われることで、マーケットの独自性を高める。それと同時にマーケットが都市の歴史的コンテクストや文化背景を強調する。そんな相乗効果があるのだ。
■クリマスマーケットのデザイン
当連載で以前にも触れたが、ドイツにおける持続可能な都市計画は、「経済」「社会」「エコロジー」の3つの側面から構想される。これは理解しやすいが、重要なのはその基盤に「文化」「価値観」「アイデンティティー」が置かれている点だ。それは多くの市民が都市に対して帰属意識や、精神的な距離の近さを感じていることが重要で、これによって都市という単位の社会にダイナミズムが起こる可能性が高まる。クリスマスマーケットは、この基盤を支える重要な要素という側面がある。
先述のような、グリューワインを飲んだり、軽食を食べながらの社交は、「社会のリビングルーム」の特徴が明確に表れる。これだけでも十分に「我々の都市」という気持ちを高めるだろう。だがクリスマスマーケットは、それ以上に社交や市民参加が促進されるようにもデザインされている。
エアランゲンのマーケットには簡易舞台が作られるが、毎日のように、学校やNPOに相当する組織の合唱団や楽団が音楽を奏でる。彼らはプロではないが、それでも生演奏はマーケットを盛り上げる。そして、演奏者の家族や友人なども結果的に演奏を聴きに来ることも多いだろう。
また、マーケットの一角に作られた「ボランティア・スタンド」では、フェアトレードや子どもの権利保護、農場での教育プログラムの実施などを行う30を超える数の非営利組織や財団のスタッフが日替わりで駐在する。このスタンドでは自分たちの手作り製品の販売による資金集め(寄付活動)や、団体の活動の紹介や対話などを行っていくのだ。
■社会的な都市の持続可能性を担っている
ドイツのクリスマスマーケットは「外から人を呼び込む」といった観光資源の側面もあるが、むしろ地域社会とのつながりや文化的アイデンティティーを強化する重要な役割を果たしている。エアランゲン市におけるマーケットは、「社会のリビングルーム」として機能し、市民同士の交流や多様性への理解を促進する場となっている。そして、商業イベントというよりも、歴史的背景や文化的文脈に根ざしている側面について触れた。
今日、都市の発展で、基本的に考えなければいけないのは「持続可能性」である。それに向けて、都市を動かすのは言うまでもなく「人」である。小さな村なら、最初から皆「顔見知り」で、コミュニティーができている。しかし、都市とは基本的に「見知らぬ人」の集まりである。だからこそ知り合うきっかけ、多い社交機会やさまざまなコミュニティーが必要なのである。クリスマスマーケットは持続可能な都市作りの礎石のひとつなのだ。

高松 平藏 (たかまつ・へいぞう)
ドイツ在住ジャーナリスト
ドイツの地方都市エアランゲン市(バイエルン州)および周辺地域で定点観測的な取材を行い、日独の生活習慣や社会システムの比較をベースに地域社会のビジョンを探るような視点で執筆している。日本の大学や自治体などでの講義・講演活動も多い。またエアランゲン市内での研修プログラムを主宰している。 著書に『ドイツの地方都市はなぜクリエイティブなのか―質を高めるメカニズム』(学芸出版)をはじめ、スポーツで都市社会がどのように作られていくかに着目した「ドイツの学校には なぜ 『部活』 がないのか―非体育会系スポーツが生み出す文化、コミュニティ、そして豊かな時間」(晃洋書房)など多数。 高松平藏のウェブサイト「インターローカルジャーナル」















