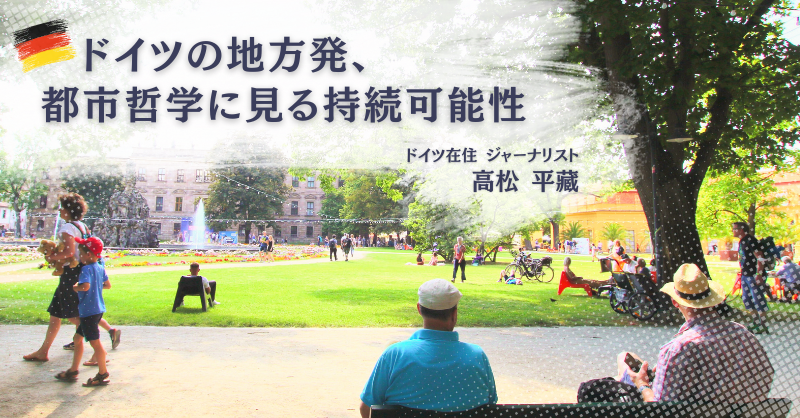 |
いささか古い「朝の習慣」でいえば、日本で人々がモーニングコーヒーを片手に「全国紙」を読むのに対し、ドイツの人々の場合は「地元紙」が主流である。ドイツでは人口1万人ほどの自治体でも町の名前がついた新聞が発行されているケースもあり、「地元紙」があることがごく普通。そして、その地域の“生きたデモクラシー”の推進役と言ってよい。なぜ、ドイツではそれほどに地方紙が重要なのか、を考えてみた。
■地域のデモクラシーと地方紙の役割
ドイツ全体をみると、新聞の発行部数は低下傾向にあり、電子化の傾向も強い。しかし2024年第3四半期のデータによると、全国で303の地方紙が、合わせて日々800万部以上発行されている。これは地域ニュースの重要性を示しており、地方紙は地域社会の声を拾い上げ、政治や行政の監視役としても機能している。
地方紙が重要なのは、一つに情報提供以上の機能を果たしているからだ。市民が自分たちの暮らしに直結する情報を得られる場であると同時に、意見交換や議論の場としても機能している。例えば、筆者が住む人口約12万人のエアランゲン市でも『エアランゲン新聞』が発行されているが、読者投稿欄があり、市民が日常的に意見を発信する機会が設けられている。これはソーシャルメディア以前から存在する、地域密着型の双方向コミュニケーションの一例だ。
■地方紙が担う「情報哲学」と市民社会
日本では報道機関への批判として「マスゴミ」という言葉があるが、これは「マスメディア」を批判していると思われる。あえて言い直すと、これはマスメディアの情報の「扱い方」についての問いだろう。この理解から言えば「ジャーナリズム」を問うているといえる。
「ジャーナリズム」にはイズムと言う接尾辞が入っている。思想とか哲学といった意味だ。つまり、ジャーナリズムとは情報の収集・加工・発信における哲学を指す「情報哲学」という説明がつく。
とりわけ、デモクラシー国家では、ジャーナリズムとは市民社会のデモクラシーが理想的に機能するための「情報哲学」である。単純化するなら、メディアは「ジャーナリズム」の入れ物だ。
ともあれ、地域社会でジャーナリズムにのっとった地方紙がドイツの自治体にはある。情報提供以上の役割があることは先述したが、報道の指針として「プレスコード」が作られている。これは「事実の尊重」「人間の尊厳の保護」、事実を曲げない編集と、後に判明した虚偽や申し立てに対する訂正、不正な個人データや情報資料の取得は行わない、広告と報道の分離などの16項目でできている。いわば「情報哲学」の実践の指針である。
■ジャーナリズムの独立性を強調する地方紙
 「意見がいつも一つとは限らない もっと地域に根ざして、もっと多様な視点を、もっと読む楽しさを」。編集長の写真が前面に出たニュルンベルク新聞の広告。他のジャーナリストの写真が使われたバージョンもいくつかあった(ニュルンベルク駅構内で、筆者撮影)
|
地方紙が果たす役割の一つに、「権力の監視」がある。これは地方紙が地域社会における独立したジャーナリズムを実現しているからこそ可能になるものだ。しかし、地方紙がこの独立性を維持するためには、ネタ元である広報担当者との健全な関係性が重要だ。
広報担当者は、組織や自治体の立場を代弁し、メディアと市民に情報を提供する。一方、地方紙はその情報を受け取りつつ、第三者的な視点から検証・解釈し、読者に届ける。
基本的にドイツは教育と職業の関連性が高く、いわゆる「ジョブ型雇用」を地でいく社会だ。ジャーナリストも広報担当者も実は職業的には同じで、ジャーナリズムやそれに類する教育を受けているケースが多い。だから、ジャーナリストが広報担当者へ転身することはよくある。その点で、構造的には「馴(な)れ合い」が生じるリスクもないわけではないが、両者が「情報哲学」に基づき、独立性を確保している限り、こうした関係は相互補完的に機能する。
例えば、地方自治体が発行する官報は、地域情報を網羅的に提供する点では有用だが、第三者的視点に欠けるという課題がある。2018年にバーデン=ヴュルテンベルク州で、ある自治体の官報が「新聞形式の記事」を掲載した結果、地元紙が訴訟を起こした。この事例は、ジャーナリズムの独立性が民主主義において不可欠であることを象徴している。
広報担当者は地方紙にとって欠かせない情報提供者である一方で、その情報がどのように読者に届けられるかは、地方紙が持つジャーナリズムの哲学に委ねられる。地方紙が独立性を堅持することで、読者は信頼性の高い情報を受け取ることができる。こうした点からも、地方紙が地域のデモクラシーを支える土台として機能していることが分かる。
■SDGsの16番目
市役所では頻繁に記者会見が行われるが、ジャーナリストなら誰でも参加できる。デモクラシーの観点から日本の「記者クラブ」はよく攻撃されるが、おそらくドイツで記者クラブを作るとなると、広報担当者自身が大反対するのではないだろうか。彼ら自身がデモクラシーにおけるジャーナリズムが不可欠であることを当然と考えているからだ。
地方紙はSDGsの目標の中でも特に16番目に関連性が高い。これは、平和で誰もが参加できる社会を築き、司法へのアクセスを確保し、制度を強化することが、民主主義の根幹を成すからだ。地域に根ざした生きた民主主義が求められるのは、まさに人々の生活に密接に関わるからである。
日本でも戦前は地方紙が豊かで、多様な声が反映されていた。しかし、戦時中の情報統制によって「一県一紙」の体制が確立し、その影響は戦後も続いた結果、全国紙主流の状況が生まれた。それでも、地域に根ざした元気な地方紙がないわけでもない。皆さんの地方の「ジャーナリズム」は健全だろうか?

高松 平藏 (たかまつ・へいぞう)
ドイツ在住ジャーナリスト
ドイツの地方都市エアランゲン市(バイエルン州)および周辺地域で定点観測的な取材を行い、日独の生活習慣や社会システムの比較をベースに地域社会のビジョンを探るような視点で執筆している。日本の大学や自治体などでの講義・講演活動も多い。またエアランゲン市内での研修プログラムを主宰している。 著書に『ドイツの地方都市はなぜクリエイティブなのか―質を高めるメカニズム』(学芸出版)をはじめ、スポーツで都市社会がどのように作られていくかに着目した「ドイツの学校には なぜ 『部活』 がないのか―非体育会系スポーツが生み出す文化、コミュニティ、そして豊かな時間」(晃洋書房)など多数。 高松平藏のウェブサイト「インターローカルジャーナル」















