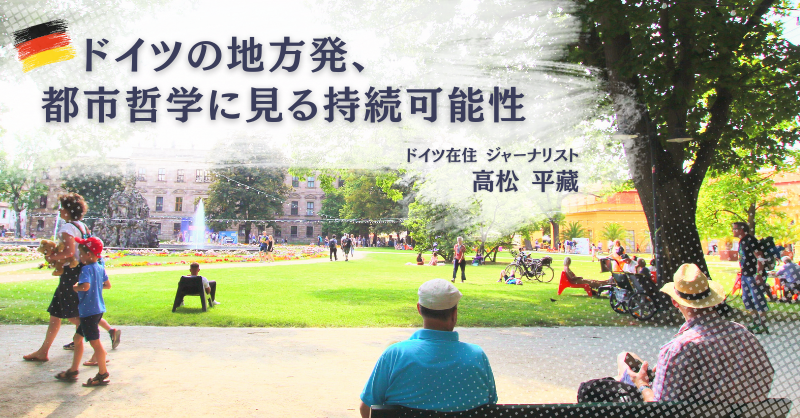 |
ドイツの都市計画において、「持続可能性」は単なるスローガンではなく、都市の根幹を成す哲学そのものだ。前回まで、筆者が住むエアランゲン市(バイエルン州、人口約12万人)の事例とそこから見いだせる哲学を紹介してきた。
今回は、持続可能な都市計画の戦略に、どういう考え方や哲学が見いだせるのかを見ていきたい。その経営戦略とは下記の図である。これはニュルンベルク市(バイエルン州、人口約53万人)の持続可能な都市計画の概念図だが、エアランゲンをはじめ類似の図は散見されるので、ドイツの広範囲で理解されているものだろう。また私個人の記憶では遅くとも2010年代初頭に、都市計画の分野の資料をあさる中でよく見かけた。
 ドイツで散見された持続可能な都市計画の戦略図。基礎部分がなければ、長期的で包括的な都市計画は難しい
|
簡単に図を紹介しておくと、経済、社会、エコロジーで構成された上部構造、その基盤となる文化、価値観、アイデンティティの重要性を示している。順番に検討していこう。
■ドイツ都市計画の隠れた強みとは何か?
この戦略図の上部構造はもっとも「分かりやすい」部分である。経済政策、福祉サービス、環境保護など、具体的な施策として実行される部分で、相互に関連性があることを示している。この3つの観点から自治体の全体を確認し、そしてバランスを取る必要があるということだ。言い換えれば、持続可能性が実装の評価の指標のような役割を果たしている。
次に「基盤」となる自治体の「文化、価値観、アイデンティティ」を見ていこう。これらは、いわば都市の根幹を形成する要素であり、目には見えにくいが、都市の個性や方向性を決定付ける重要な役割を果たしている。
この基礎部分がドイツの都市の長期的視点をつくり、一貫した発展を遂げられる背景だろう。文化や価値観は簡単には変わるものではない。それゆえ、首長や「与党」が変わっても、経済状況が変動しても、都市の根本的な方向性は保たれるのだ。
特に「文化」は、都市の精神とも言える存在だ。ドイツの都市における文化は、単なる芸術作品や伝統行事を指すのではない。それは都市の歴史、市民の生活様式、そして未来への展望を包含する広範な概念だ。「人口が多いだけでは都市ではない」という見方がドイツには見いだせるが、文化がなければ「都市らしさ」が形成できない。
例えば前回の「ドイツの町にとって芸術祭が重要な理由」で紹介したのは、「自由(な意見表明)」という根底にある価値観だ。これは単なるイベントの開催ではなく、都市の文化的土壌に根ざした自由な意見表明とその交換を示している。また、第3回「どう作る? ドイツのようなウォーカブルなまち」では、歴史的建造物の保存を通して都市の「アイデンティティ」をどのように考えたかという問いがある。これは都市の文化的連続性を保ちながら、現代的なニーズに応える都市設計の哲学を反映している。
このように、ドイツの都市計画における「文化、価値観、アイデンティティ」は、過去と現在、そして未来をつなぐ重要な要素として機能している。また、それは単なる観光資源でもない。市民の日常生活や都市の意思決定プロセスにまで深く浸透し、都市の持続可能な発展を支える基盤となっている。
■上部構造と基盤をつなぐ重要な中間部分
この戦略図を理解する上で重要な要素が、上部構造と基盤の間にある中間部分だ。図では単純な線で表現されているが、ここには実際にはさまざまな要素が含まれている。例えば、都市計画法や建築基準法などの法的枠組み、都市計画局や環境局といった行政組織、そして市民参加の仕組みがここに該当する。
これらの制度や仕組みは、上部構造に示された経済、社会、エコロジーの3つの側面を具体的な政策として実現する上で不可欠な要素だ。いわば、理念を現実の施策に変換する装置が詰まっていると言えるだろう。
さらに、この中間部分は上部構造と基盤を有機的につなぐ重要な役割も果たしている。例えば、市民参加の仕組みは、基盤にある文化や価値観を上部構造の政策決定プロセスに反映させる重要な橋渡し役だ。市民の声を直接政策に反映させることで、地域の特性や住民のニーズに合った都市計画が可能になる。
また法制度や行政システムは、上部構造の政策が基盤の文化的アイデンティティと整合性を保つよう調整する機能がある。例えば、歴史的建造物の保存に関する法律は、経済発展と文化遺産の保護のバランスを取る役割を果たす。
このように、中間部分は上部構造と基盤の間で双方向的な調整を行い、都市の持続可能な発展を支える役割を果たしているかたちだ。
■基盤部分は不可欠だ
SDGsは「経済・社会・エコロジー」の上部構造の部分を17のカードに分けて表現されたものと言える。この3つのバランスの重視に至るまでは欧州の19世紀の工業化の歴史が非常に大きい。この経緯は別稿で触れていく。
またSDGsは前文を読むと分かるように「人権と人間の尊厳」を尊重することを中心に据えて構築されている。これが、図の「基盤」の価値観に相当する。そして人権や人間の尊厳も、欧州で育まれた価値観だ。
SDGsは決して欧州哲学を元に作られたわけではないが、極めて類似しているのが見いだせる。
このような考え方が、今回見てきた持続可能な都市計画の戦略にも十分に反映されているのが分かる。そして、自治体は多くの市民が実際に生活し、極めて具体的な「社会」をつくっていく。それゆえにどのような「都市の文化」「都市のアイデンティティ」「都市の価値観」を作り、練っているのかと言うことが鍵になる。
いささか乱暴な例えで言えば、企業においても持続可能性を踏まえた経営をする場合、優れた経営者なら「企業の文化」「企業のアイデンティティ」「企業の価値観」を明確にする必要性を知っているはずだ。
確かに、「あらゆる老若男女」の集合体である自治体とは異なり、企業は「労働人口」だけの組織だ。しかし、経営体として考えなければいけないところは同じと言えるだろう。読者諸氏の自治体の「持続可能性」の戦略はどのような構造になっているだろうか?

高松 平藏 (たかまつ・へいぞう)
ドイツ在住ジャーナリスト
ドイツの地方都市エアランゲン市(バイエルン州)および周辺地域で定点観測的な取材を行い、日独の生活習慣や社会システムの比較をベースに地域社会のビジョンを探るような視点で執筆している。日本の大学や自治体などでの講義・講演活動も多い。またエアランゲン市内での研修プログラムを主宰している。 著書に『ドイツの地方都市はなぜクリエイティブなのか―質を高めるメカニズム』(学芸出版)をはじめ、スポーツで都市社会がどのように作られていくかに着目した「ドイツの学校には なぜ 『部活』 がないのか―非体育会系スポーツが生み出す文化、コミュニティ、そして豊かな時間」(晃洋書房)など多数。 高松平藏のウェブサイト「インターローカルジャーナル」















