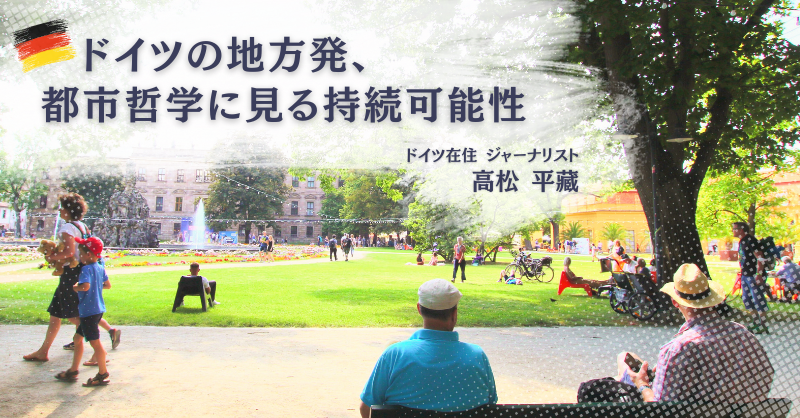 |
10年以上前のことだが、ドイツにリサーチに来た研究者の知人が、ついでに筆者を訪ねてくれ、意見交換の機会を持った。その中で「地方行政でインタビューをしたが『まちづくり』というのが伝わらない」という話が出てきた。
それもそのはずで、「まちづくり」は日本独自の文脈の中で使われている言葉だからだ。ドイツ語でぴったり直訳できるものがない。
「まちづくり」は戦後、行政からの都市計画に対し、住民参加を重視した参加アプローチとして1960年代に登場した。「トップダウン」から「ボトムアップ」へのプロセスを目指したものである。1970年代には市民参加の議論がさらに広がる。「まちづくり」の「まち」の範囲は極めて柔軟だ。また児童教育、高齢者問題、福祉、コミュニティ構築、街並みなどカバーする課題も極めて広い。言い換えれば定義が曖昧で、法的な背景もない。
■全体を見ながらの都市づくり
ではドイツの都市づくりはどうしているのだろうか。まず言葉から整理すると類似の言い方に「都市計画」「都市デザイン」「都市開発」といった言葉がそれに当たる。またドイツ語の「都市(Stadt)」自体、大まかには日本と同じ意味だが、やはりドイツの文脈の中で成り立っており、日本の「都市」とは異なる。
その上でドイツの「都市を作る」仕組みを見ると、都市全体の利用の大枠を決め、具体的に建物を建てる時には法的拘束力のあるルールがある。つまりドイツは常に都市全体を見ながら都市づくりをしていると言える。
さらに、その視点を補足するのが統計局だろう。ドイツの自治体の統計局は常にさまざまな調査を事細かに行っている。筆者が住むエアランゲン市(人口約12万人)を見ると、「統計・都市調査局」という部署を置き、自治体内の人口統計や選挙結果、土地利用などをはじめ、教育や治安、中心市街地の利用状況やニーズ、健康など頻繁に統計資料を作成している。これらは議員の政策立案の大きな手がかりになることもある。職員も専門知識を持ったスタッフが継続的に取り組んでいる。もっともこれはドイツの行政マン全般に言えることだが、基本的に他部署への人事異動はなく、各部署に必要な専門教育を受けた人物が働いている。
■計画段階から全体像と実践的視点が加わる
 ドイツの多くの都市には、発祥地の中心市街地の立体モデルが置かれている。これは「都市全体を俯瞰する」という傾向と重なって見える。写真はエアランゲン市の中心市街地のモデル(筆者撮影)
|
都市計画の中で市民参加は当然のごとく行われる。いわゆる開発対象になる地区の住民たちが集まる機会があるが、ここでは別のケースを紹介しよう。
筆者は一度、エアランゲン市のスポーツ関係部署の会議にオブザーバーで参加したことがある。議題はある地区に新しい屋外型のスポーツ施設を作ることだった。その会議には都市計画局のスタッフの他に、スポーツクラブのスタッフなども入っていた。
スポーツクラブについて、少し説明を加えると、NPOに相当する組織で運営されていて、小学生から年金受給者にまで至る、老若男女がメンバーだ。もちろん試合を前提で頑張る人もいるが、多くは健康や運動、仲間との時間を楽しむ人たちで、「スポーツを軸にしたコミュニティ」と捉えるのが妥当だろう。歴史も長く、数も多いので、ドイツの人々にとって、あるいは都市にとって、欠かせないリビングスタンダードになっている。エアランゲン市でもそんなスポーツクラブが100程度ある。
会議の話に戻すと、ある地域に屋外型スポーツ施設を作るといった場合、自治体全体を俯瞰(ふかん)できる都市計画局、そして市民スポーツの専門NPOがその会議に入っているのだ。しかも予算案を作る前の段階でのことである。この日の会議の結論は、対象地区のNPO全員に参加してもらう会議を設定するということだった。ちなみにNPOに相当する組織もドイツでは多い。エアランゲン市だけでも800程度はある。もう少しリアルな数字を出すならば、同市内の4000人ほどの地区でも5、6はあり、その中の一つはスポーツクラブだ。
■全体最適と部分最適、そしてデモクラシー
以上のように見ていくと、特に日本の都市の作り方は自治体内の部分最適化の傾向が強い。というのも、実際の建物が建てられる時に、ドイツに比べると規制が緩く、全体的な景観の統一が取りにくい。さらに「まちづくり」はボトムアップのプロセスを指向するが、自治体内のごく一部のみが対象だからだ。
それに対して、ドイツは自治体全体の全体最適を目指す方向性が強い。その背景には、まず土地利用の方向性を決める部分があり、それを補足する「全体像を常に見るための装置」もある。代表的な例として今回は統計局を紹介したが、他にもいくつかある。その上で土地の所有者の自由度が制限されており、例えば街の景観などの統一感につながる。また持続可能性の高い都市づくりには、全体像を常にモニタリングすべきで、その点ではドイツのスタイルは相性が良いと言える。
それから「まちづくり」でも重要視されていたのが市民参加だ。これはデモクラシーの質に関わるテーマである。ドイツの場合、そもそも「下からのデモクラシー」を重視しており、例えばバイエルン州の憲法でも明記してある。デモクラシーで重要なのは誰でも、平等な関係の中で自由な意見を述べ、参加することにある。しかし、自分の意見通りになるわけではない。意見が出た後は「全体としての共通の善きこととは何か」を考えながら妥協点を探るプロセスを経て決定する。これが共生の方法としてのデモクラシーである。ドイツの地方都市を見ると、この方法に参加するための教育が学校でも行われ、成人になってからも、さらにデモクラシーへの参加能力を伸ばす仕組みがある。
デモクラシーで鍵になってくるのは対話だが、これは時間・労力という点でも必要な「対話コスト」で、ドイツはかなりかけている。例えば、エアランゲンの市街中心地で作られた歩行者ゾーンも現在の形になるまで20年近くかかっている。これを「時間のかけすぎ」と見るかどうかは読者諸氏によって異なるであろう。それにしてもドイツと日本では都市の捉え方や作り方がかなり異なることが浮かび上がる。
参考文献
Vogt Silke, Neue Wege der Stadtplanung in Tokyo: Partizipationsansätze auf der Mikroebene, dargestellt anhand ausgewählter machizukuri-Projekte in Tokyo: Iudicium, 2001.

高松 平藏 (たかまつ・へいぞう)
ドイツ在住ジャーナリスト
ドイツの地方都市エアランゲン市(バイエルン州)および周辺地域で定点観測的な取材を行い、日独の生活習慣や社会システムの比較をベースに地域社会のビジョンを探るような視点で執筆している。日本の大学や自治体などでの講義・講演活動も多い。またエアランゲン市内での研修プログラムを主宰している。 著書に『ドイツの地方都市はなぜクリエイティブなのか―質を高めるメカニズム』(学芸出版)をはじめ、スポーツで都市社会がどのように作られていくかに着目した「ドイツの学校には なぜ 『部活』 がないのか―非体育会系スポーツが生み出す文化、コミュニティ、そして豊かな時間」(晃洋書房)など多数。 高松平藏のウェブサイト「インターローカルジャーナル」















