 |
~ ビジネスと社会課題解決を両立させ、「らしさ」で競争優位を創り出す!待望の戦略メソッド ~
「HSR」って、ご存じですか?
大学医学部の医局や医師会・学会、大病院からの講演招聘を受けます。医療機関では、「HSR」に関心が高まっています。「時代に選ばれ、次代にも輝き続ける」ための戦略メソッドは、企業も病院も共通です。その原理原則は「現代社会への対応力」 、すなわち「SR(Social Responsibility)」です。病院(Hospital)では「HSR」。さらに、「らしさ」が発揮できれば、「病院ブランディング」につながります。
「社会」を豊かにする、幸せにする
 |
変わりゆく現代社会のもとで、企業はもちろん、「病院」という組織も、「社会」との新しい関係づくりが求められるようになってきました。
創立時より長きに渡り発展してきている組織は、おしなべて「あるべき姿」に「社会を豊かにする」「社会を幸せにする」などと掲げています。ところが、時代とともに「社会」の関心や価値観が変化するにつれ、組織に期待される役割や責任も、それを映し出して変化します。したがって、目まぐるしく変化する社会のニーズや価値観を捉える感性の鋭さを備え、対応してこそ、いまの社会を豊かに、幸せにできます。
いつの時代にも、磐石な経営基盤を確保しつつ、あらゆる変化に柔軟に対応していくことこそが、「SR(Social Responsibility)」の根幹にあります。
ここにきて、「変わったところ、変わろうとしているところ、そうでないところ」が明白になってきているようです。「今どき、そんなことをしているのか」「今どき、そんなこともしてないのか」と、社会から烙印を押されてしまうと組織存亡の危機にさらされるといっても過言ではありません。
 |
「HSR(Hospital Social Responsibility)」は、時代が求める競争力
「社会的責任(SR)に関する国際規格」(ISO26000)は、すべての組織を対象としています。今日、社会的存在意義を強く問われる病院等医療機関においても、HSR(Hospital Social Responsibility:病院の社会的責任)が注目されています。
医療機関の第一義的使命は、質の高い医療技術やサービスを安定的に提供できることですが、かたわらで医療や介護の現場において、ヘルスケアスタッフによるトラブルや事件を繰り返せば、医療機関の信用は完全に失墜してしまいます。
そして、「病院」は地域社会の重要な一員であり、責任も重大です。とりわけ病院の場合は、一般企業よりも地域性が強く、日頃から「潜在顧客」でもある地域住民に支持されることはとても大事な要素です。
「HSR」という新しい用語は、病院経営者に対して、また何か新しい義務が発生するかのように思われがちですが、「先進のCSR」を反映した「HSR」は、本業とのトレード・オフではなく、時代が求める競争力につながります。
医師を含め医療従事者は、元々仕事内容自体の公共性が高く、医療には高度な専門性をもち高邁な倫理観に裏打ちされた職業としての使命感があり、「社会貢献」をしているという自負が強くあります。逆に、それが起因して、改めて「CSR(HSR)」という概念を捉えなおす必要性を感じていなかったとも推察されます。
しかしながら、今日の医療界は、未だ経験したことのない厳しい環境に直面しています。医師の不足・偏在、看護師の不足、医療の質と安全に関わる要求水準の高まり、リスクマネジメントのコスト増、アメニティ要求水準の変化・高度化・多様化、医事紛争増加や刑事告訴、労働時間管理、情報開示要求の高まり、医療の財源の枯渇と医療費増の抑制策など、難題山積といわれています。
そして、いまや患者は「患者様」と呼ばれ、家族も含め、インフォームド・コンセント、セカンドオピニオンは当たり前、「医師の方が圧倒的に情報を持っている」という「情報の非対称性」も昔ほどではありません。
さらには、2017年5月30日施行の改正個人情報保護法に基づく「要配慮個人情報」の取扱いや、レントゲン・CT等の医療用放射線検査による「医療被ばく」にも敏感になり、患者の尊厳と生活の質(QOL:Quality Of Life)の概念等も着実に浸透しつつあります。
患者の視点に立ち、患者本位の医療提供を実現するためには、患者とのリレーションシップを強化する必要があります。そのためにはまず、患者が医療に関する情報をより容易に得られるようにし、また適切な医療機関や治療方法などを選択できるよう医療機関として心がけることが必要です。
また、医療サービスの質の向上や医療事故の軽減に努め、さらに良好なコミュニケーションを心がけることで、患者満足を高めることが求められています。そのためにも、時代と調和した医療従事者の資質向上は喫緊の課題といえます。
その上、病院を取り巻くステークホルダーは、患者・家族だけではなく、病院職員・取引先・地域社会、さらには厚生労働省など行政もあります。ちなみに、「ステークホルダー」という言葉は、大変ポピュラーに使われるようになりましたが、そのまま「利害関係者」と捉えてしまうと、「利害」という言葉が包含する対立概念によって違和感のある方もおられるかもしれません。
なのでここでは、企業(病院)にとって、「欠くべからざる存在」であり、「企業(病院)を支える存在」という解釈をお薦めします。相身互い、持ちつ持たれつの関係にある人々です。こうした人々から信頼され、応援してもらってこそ、持続的成長ができるというのが、CSR(HSR)の眼目です。
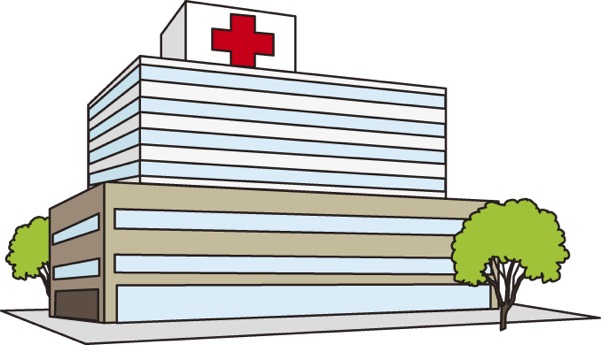 |
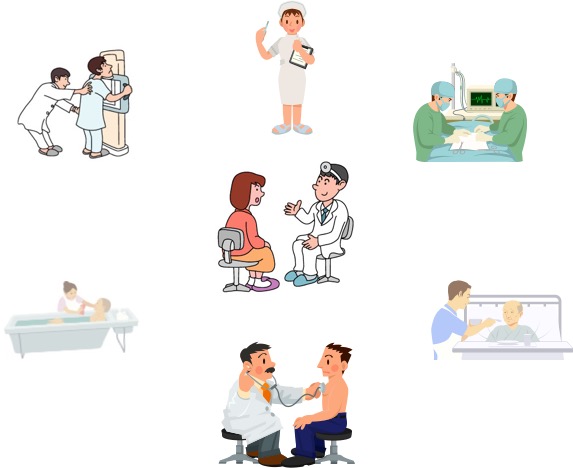 |
「すばらしい病院(Excellent Hospital)」であるためには、「地域に貢献する誠実な組織として、安全で良質な医療サービスを提供する」という基本姿勢のもと、患者や地域社会をはじめとするステークホルダーの意識や価値観の変化にしなやかに対応できる病院経営が求められています。
戦略的に「HSR」に取り組み、現代社会の要請や期待にきちんと応えることで、「病院の評判(Hospital Reputation)」を高め、それが「見えざる資産(無形資産)」として病院価値向上の原動力となります。
変わりゆく社会の潮流を捉え、患者をはじめとする地域社会から、これまで以上に「○○病院なら信頼できる」と言われる関係を築くためには、一人ひとりの病院スタッフが「誇りと自覚」をもって、自主的・主体的に「先進のCSR(HSR)」を担うことが要諦です。
時代に選ばれ、次の時代にも輝き続ける企業(病院)であるために、「社会対応力」を備え、「自社(自院)らしさ」を発揮することによって競争優位を創り出す戦略メソッドが「CSR(HSR)ブランディング」です。
編集部からお知らせ
☆編集部から参考情報です。8月に、細田さんの「新しい経営のあり方」研修が開催されます。ご関心のある方は以下より詳細をご覧下さい。医療機関の皆さまもどうぞ!

細田 悦弘 (ほそだ・えつひろ)
公益社団法人 日本マーケティング協会 「サステナブル・ブランディング講座」 講師 一般社団法人日本能率協会 主任講師
1982年 中央大学法学部卒業後、キヤノン販売(現キヤノンマーケティングジャパン) 入社。営業からマーケティング部門を経て、宣伝部及びブランドマネジメントを担当後、CSR推進部長を経験。現在は、企業や教育・研修機関等での講演・講義と共に、企業ブランディングやサステナビリティ分野のコンサルティングに携わる。ブランドやサステナビリティに関する社内啓発活動や社内外でのセミナー講師の実績豊富。 聴き手の心に響く、楽しく奥深い「細田語録」を持ち味とし、理論や実践手法のわかりやすい解説・指導法に定評がある。 Sustainable Brands Japan(SB-J) コラムニスト、経営品質協議会認定セルフアセッサー、一般社団法人日本能率協会「新しい経営のあり方研究会」メンバー、土木学会「土木広報大賞」 選定委員。社内外のブランディング・CSR・サステナビリティのセミナー講師の実績多数。 ◎専門分野:サステナビリティ、ブランディング、コミュニケーション、メディア史 ◎著書 等: 「選ばれ続ける会社とは―サステナビリティ時代の企業ブランディング」(産業編集センター刊)、「企業ブランディングを実現するCSR」(産業編集センター刊)共著、公益社団法人日本監査役協会「月刊監査役」(2023年8月号) / 東洋経済・臨時増刊「CSR特集」(2008.2.20号)、一般社団法人日本能率協会「JMAマネジメント」(2013.10月号) / (2021.4月号)、環境会議「CSRコミュニケーション」(2010年秋号)、東洋経済・就職情報誌「GOTO」(2010年度版)、日経ブランディング(2006年12月号) 、 一般社団法人企業研究会「Business Research」(2019年7/8月号)、ウェブサイト「Sustainable Brands Japan」:連載コラム(2016.6~)など。









