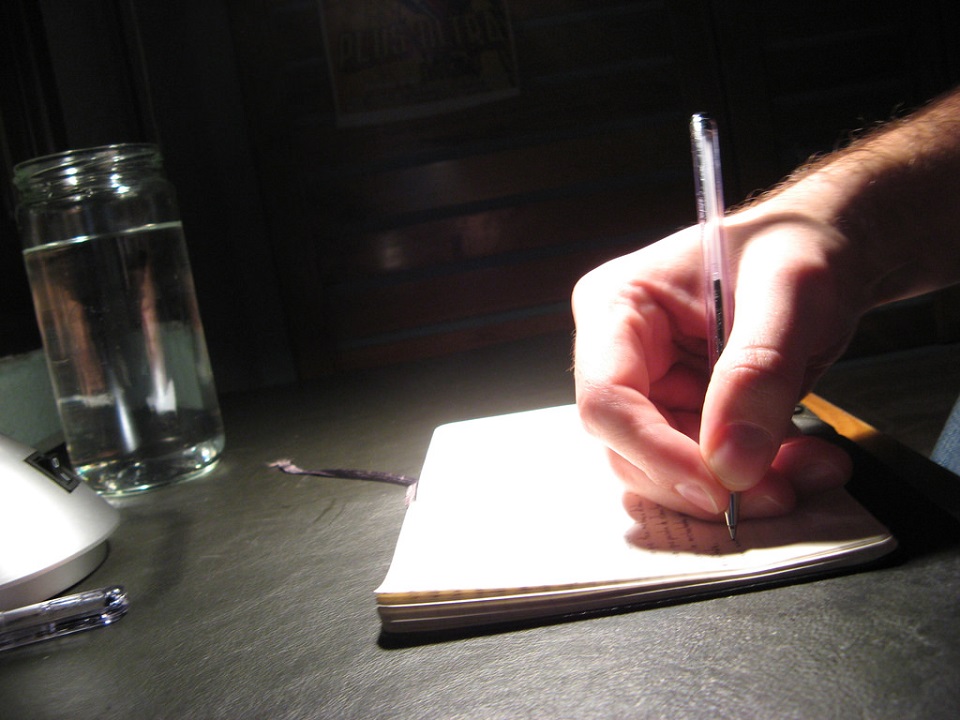 image credit:Tnarik Innael
|
近年、「CSV(共通価値の創造)」が注目されるようになりました。
2007年にネスレのピーター・ブラベック前CEOが提唱し、2011年にハーバードビジネススクールのマイケル・ポーターが世界に発信した考え方で、「ビジネス戦略として社会的課題の解決に資するとされる製品・サービスや事業を開発し、経済的価値とともに社会的価値を創造する」ことを提唱しています。
2015年に採択されたSDGsに言及がある「アウトサイド・イン」の考え方も、「社会課題の解決を起点にしたビジネス創出」という意味で、CSVと同じ趣旨と言ってよいでしょう。
この雑誌の記事中、「(C)そこで出てきたキーワードが、『サステナビリティ(Sustainability=持続可能性)』である。企業がビジネスそのものを通じて、環境や社会が抱えている課題の解決を進めていこうという考え方だ」とあるのは、おそらくサステナビリティとCSVを混同したのではと推察されます。
ちなみに、CSVが日本でも流行し始めたころ、「CSRはもう古い。これからはCSVだ」という論調が見受けられましたが、これについてもCSRの本質を見誤ったものとして、2014年3月に日本のCSR専門家20人が共同で提言書を出しました。
2014年3月13日
一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)、一般財団法人CSOネットワーク
私たちは、「CSRかCSVか」という不毛な議論を避けるためにも、双方を一括りにした「CSR/CSV」という表記を使っています。この括りはISO26000のCSR定義のうち、特に「組織全体に統合され、組織の関係の中で実践される行動」に該当します。
(D) 「これまではCSRの視点で社会貢献を中心に取り組んできたが、これからはサステナビリティにかじを切る」ーーに至っては、CSRの専門家から見るとかなり理解に苦しむ表現です。
繰り返しになりますが、CSRやCSVは「手段」(ツール)であり、サステナビリティは「ビジョン」なのですから、同列に扱うことはできません。
「CSRという言葉から逃げない」
さて、以上のように、「CSRはもう古い。これからはCSVだ。サステナビリティだ」という論調がたまに出てきますが、これではCSRの本質を正しく理解し、企業経営の根幹に統合していくという本来の姿からはかけ離れていくばかりです。
この数年で、「CSR部」を名称変更してサステナビリティなどの名称に変えた企業もありました。その理由としては「CSRでは従業員に理解してもらえない」「CSRという概念は難しすぎる」「欧米企業では使っていない(事実ではありません)」というものが多かったようです。
ただし、筆者が見る限りは、CSR部の名称を廃した企業においてCSR活動が進化した例は決して多くはありませんでした。CSRやCSV、そしてサステナビリティという言葉を正しく理解し、正しく位置付け、組織に統合することが重要です。その中で特に「CSRという言葉から逃げない」ことが何より肝要です。
今回、このような記事が世の中に出るということは、CSRやその体系が世の中にほとんど理解されていないことが改めて分かりました。これは大変残念であるとともに、CSRやサステナビリティについての雑誌を10年間運営してきた身にとって、力の限界を改めて感じさせられました。
筆者としても、今後も、諦めずにCSRの理解と普及に努めていきたいと考えています。

森 摂(もり・せつ)
株式会社オルタナ代表取締役社長・編集長。
東京外国語大学スペイン語学科を卒業後、日本経済新聞社入社。1998年-2001年ロサンゼルス支局長。2006年9月、株式会社オルタナを設立、現在に至る。主な著書に『未来に選ばれる会社-CSRから始まるソーシャル・ブランディング』(学芸出版社、2015年)、『ブランドのDNA』(日経ビジネス、片平秀貴・元東京大学教授と共著、2005年)など。訳書に、パタゴニア創業者イヴォン・シュイナードの経営論「社員をサーフィンに行かせよう」(東洋経済新報社、2007年)がある。一般社団法人CSR経営者フォーラム代表理事。特定非営利活動法人在外ジャーナリスト協会理事長。










