「グッド・ライフ」がブランドの選択基準に
「サステナブル・ブランド国際会議2018東京」(SB 2018 Tokyo)が3月1-2日、ヒルトン東京お台場(東京・港)で開かれた。サステナブル・ブランドはサステナビリティ(持続可能性)とブランド戦略の統合をテーマに2006年に米カリフォルニア州で生まれ、国際会議は世界11カ国12都市で開催されている。今年度の世界共通テーマは「グッド・ライフの再定義」。グッド・ライフとは何か、ブランドはどう生活者のグッド・ライフに貢献できるのかなどについて議論された。
持続可能性を高め、トレード・オンへ ――新浪 剛史・サントリーホールディングス社長
 |
「事業を成長させ、自然環境を守り、社会と共生していくことは『トレード・オフ』ではない。私たちは『トレード・オン』に変えていける」。サントリーホールディングスの新浪剛史社長は、「サステナブル・ブランド国際会議2018東京」でこう語った。サントリーは「やってみなはれ」「利益三分主義」の創業精神のもと、グローバルで水を軸にしたサステナビリティの取り組みを進める。
続きはこちら
「イズム」に飲み込まれない理念ある市場をーー国連グローバル・コンパクト ボードメンバー 有馬 利男氏
|
|
国連グローバル・コンパクト ボードメンバーの有馬利男氏が「サステナブル・ブランド国際会議2018東京」に登壇した。有馬氏は基調講演「SDGsから見えてくる Good Life」のなかで、ステークホルダーとのかかわり、深刻化する社会課題、投資家の動向などビジネス環境の変化を挙げながら、「SDGs(持続可能な開発目標)に対し、企業が貢献できることはたくさんある」と訴えた。
続きはこちら
「障がい」を「価値」に変える――ミライロ 垣内俊哉社長
|
(撮影・福地波宇郎)
|
「生きることを何度もあきらめようとした。生まれたことを不幸に思っていた」――。「サステナブル・ブランド国際会議2018東京」の1日目、車いすで登壇したミライロの垣内俊哉社長は、ウェルカムスピーチをこう始めた。「それでも、視点を変えると少しずつ変わっていった。『障がい』は『価値』に変えられるはず」。そう語る垣内社長の言葉は会場に響きわたった。
続きはこちら
SDGsと金融業界ーー大和証券グループのSDGsへの取り組み
サステナビリティをどうブランディングに取り込むか
|
|
「サステナビリティをどうブランディングに取り込むか?」と題したセッションには、サステナブルなブランドの先進事例として、サントリーとプロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(P&G)が登壇。
続きはこちら
「量的」から「質的」な豊かさへ――小宮山 宏・三菱総合研究所理事長
|
|
かねてから「プラチナ社会構想」を提唱している小宮山 宏・三菱総合研究所理事長が「サステナブル・ブランド国際会議2018東京」に登壇した。社会課題が山積するなかで、持続可能な社会システムをどのように確立していけるのか。講演の内容を一部抜粋して紹介する。
続きはこちら
環境や人権に配慮した「持続可能な調達」とは
 |
企業やNPOが「サステナブル・ブランド国際会議2018東京」の「環境や人権に配慮した『持続可能な調達』とは?」と題したパネルディスカッションで、責任ある調達について議論した。パネリストは、大手調達元であるイオンと大和ハウス、サプライチェーンの持続可能性を支援している米国UL規格、児童労働問題の解決に取り組むNPO法人ACE。立ち位置の異なる4者が現状や課題を共有した。
続きはこちら
サステナブル・ブランドをつくる3つのデザイン力
 |
「サステナブル・ブランドをつくる3つのデザイン力とは?」のセッションでは、「どうしたら自社のブランドをサステナブルなものにできるか」というテーマに企業、広告代理店、メディアという異なる業種からのゲストが具体例を紹介しながらその方法論を論じた。セッションでは、企業の存在意義を高める「志す力」、社会課題をふまえて事業化していくための「アイデア発想力」、多くの人に共感を得て広げていく「巻き込む力」という3つのデザイン力が重要であり、それぞれが行き来しながらブランド力が深まることが見えてきた。
続きはこちら
世界で注目を集めている 「Good Life 2.0」とは
 |
ファシリテーターに、ソーシャル・デザイナーで「NELIS」共同代表のピーター・D・ビーダーセン氏を迎えた「世界で注目を集めている『Good Life 2.0』とは?」。サステナブル・ブランド国際会議の創設者であるコーアン・スカジニアCEOによる、米国のグッド・ライフ調査のまとめから始まったこのセッションでは、米国のカフェチェーン「パネラ・ブレッド」やアウトドアブランドのREIといった、同国を代表する大手企業による、新しい価値観におけるグッド・ライフをサポートするさまざまな企業活動が紹介された。
続きはこちら
日本でも始まった「Good Life 2.0」の潮流とは
 |
SB国際会議のグローバルテーマである「グッド・ライフの再定義」。その要となるのが、日米タイの3カ国で展開された「グッド・ライフに関する意識調査」である。セッションは、日本で調査を担当したインテージのマーケティング部マネージャー・定性ソリューションスペシャリストの星晶子氏による調査結果の発表を中心に議論が進められた。
続きはこちら
企業も「ハッピーヒーロー」に
 |
「人々がある状況を現実であると定義すれば、結果としてその状況は現実となる」ロンドンに拠点を置き、サステナビリティに関するコンサルティングを行うフテラの共同創業者ソリティア・タウンセンド氏は、米社会学者ウィリアム・I・トマスの言葉を紹介した。
続きはこちら
企業は環境技術で社会課題をどう解決していくか
 |
「企業は環境技術で社会問題をどう解決していくか?」のセッションでは、建物・街づくり、オフィス環境を専門とする企業のパネリストが、地域・街づくりの観点からテーマについての解決策を展開した。
続きはこちら
社会が応援する企業のサステナブル経営
|
|
サステナブル・ブランド国際会議初日の中でも注目を集めたセッション「社会が応援する企業のサステナブル経営とは」には、鎌倉投信の新井和宏取締役 資産運用部長、マザーハウスの山崎大祐副社長、リバースプロジェクトの龜石太夏匡代表取締役が登壇した。ファシリテーターを務めたのは近畿大学経営学部の廣田章光教授。立ち見が出るほどの熱気のなか、セッションは始まった。
続きはこちら
障がい者をイノベーターに、農業・福祉・企業が連携
 |
「パートナーと一緒になって障がい者をイノベーターにしていく」。グッドパートナーシップのセッションで、農福連携自然栽培パーティ全国協議会の佐伯康人代表理事が述べた。自然の力だけで育てる「自然栽培」を行う福祉事業所を全国に拡げ、地方にある課題解決に挑んでいる。「障がい者×自然栽培」でつながった立場の異なる4者が登壇した。
続きはこちら
日本で「エシカル消費」をメインストリーム化するには
 |
サステナブル・ブランド国際会議2018東京の「日本で『エシカル消費』をメインストリーム化するには」と題したセッションは、参加者の属性確認から始まった。ファシリテーターが、企業、学生、NPOと順番に挙手を求め、最後に「消費者の人」と問うと、会場に手を挙げない人々がいた。「いや、皆さん消費者ですよね」というところから、4人の登壇者によるエシカル消費論議が始まった。
続きはこちら
日本でも注目される「サステナビリティ経営」とは
 |
サステナビリティと経営を統合する「サステナビリティ経営」。サステナブル・ブランド国際会議2018東京で開催されたセッション「日本でも注目される『サステナビリティ経営』とは?」に味の素、花王、リコーの3社が登壇し、どのように取り組んでいるか、具体例を挙げながら議論した。
続きはこちら
BtoB企業にCSR/CSVを導入するためのポイントとは
 |
「BtoB企業にCSR/CSVを導入するためのポイントとは」のセッションでは、商取引の規模や経済に与える影響が大きく、期間が長期にわたり、変更しづらいBtoB企業が、CSR/CSVに向き合わなくて果たして良いのだろうかといった点を踏まえ、3者のパネリストによるプレゼンテーションが行われた。
続きはこちら
SDGsを事業やマーケティングにどう生かしていくか
 |
SDGsは、今や多くの企業にとって進むべく指針となりつつある。SDGパートナーズの田瀬和夫CEOをファシリテーターに迎え、先駆的な3社の事例を通じ、事業やマーケティングにSDGsをどのように生かせるかについて、議論が交わされた。
続きはこちら
SDGsをどう経営に統合するか
 |
2015年に国連で採択されたSDGs(持続可能な開発目標)。認知度は高まってきたが、活用方法としては事業と17目標のアイコンを関連付けるにとどまっていることが多い。サステナブル・ブランド国際会議では、その次の段階として、SDGsをどのように経営に統合していけば良いのかが議論された。
続きはこちら
統合的思考とESG経営・ESG投資の重要性
 |
2015年に年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が国連責任投資原則(PRI)に署名した。これにより、日本でもESG(環境・社会・ガバナンス)投資へのシフトが進み、企業も非財務情報の開示がより一層求められている。セッション「経営の統合的思考とESG経営/ESG投資の重要性とは」では、丸井グループの青井浩代表取締役社長、大和総研の河口真理子調査本部主席研究員、サンメッセの田中信康執行役員が議論を深めた。
続きはこちら
地方創生と観光――新たな関係を考える
 |
サステナブル・ブランド国際会議2018東京では旅と観光の専門家3人が、「2030年に向けてあるべきGood Destinationを考える 地方創生と観光――新たな関係を考える」をテーマに語り合った。ファシリテーターは、一般社団法人モア・トゥリーズの水谷伸吉事務局長が務めた。
続きはこちら
地方創生の「ソーシャル・デザイン」をどう加速させるか
 |
地方創生をテーマにしたセッション「地方創生のカギとなる『ソーシャル・デザイン』をどう加速させるか」には、地方創生の現場で活躍する3人が登壇した。ファシリテーターは、サステナブル・ブランド国際会議東京 アカデミックプロデューサーの青木茂樹氏が務めた。
続きはこちら
国籍の壁を越え持続可能性を社内浸透させるには
 |
「企業は社員の国籍・言葉の壁を越えてどう持続可能性を共通認識してもらうか」のセッションでは、日本を代表する企業のCSR担当者、関連部署に従事するパネリスト4者が、自社での取り組みを踏まえたプレゼンテーションを行った。
続きはこちら
次の時代を元気にする企業を地方で増やすには
 |
「次の時代を元気にする企業を地方でどう増やせるのか」をテーマに行われたセッションには、楽天の小林正忠CPO(Chief People Officer)・常務執行役員と中央葡萄酒(甲州市)の三澤彩奈取締役・栽培醸造部長、モンベルの竹山史朗常務取締役・広報本部長が登壇した。ファシリテーターを務めたのは、一般社団法人日本能率協会の細田悦弘主任講師だ。
続きはこちら
日本で「クリーンエネルギー」をどう普及させるか
 |
事業運営に使う電力を、100%再生可能エネルギーで調達することを目指す「RE100」へ加盟する日本企業が増えてきた。2016年度は1社もなかったが、今年3月末時点で6社となった。「日本の経済・社会にクリーンエネルギーをどう普及させるか」のセッションでは、3月に加盟を発表した大和ハウス工業の小山勝弘環境部長が登壇した。
続きはこちら
世界に誇れるサステナブルシティの姿とは
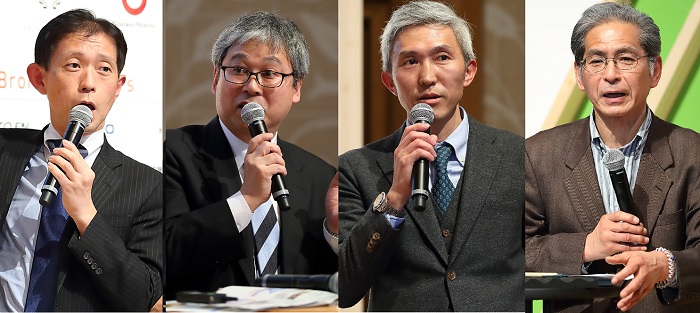 |
サステナブル・ブランド国際会議で開催された「2030年に向けてあるべきGood Cityを考える――世界に誇れるサステナブルシティの姿」のセッションでは、建築・不動産および、まちづくり・建築認証の分野から3人のパネリストがプレゼンテーションを行った。
続きはこちら
日本社会に適したダイバーシティ推進とは
 |
「日本に適応した未来を拓くダイバーシティ推進で持続可能社会へ」セッションでは、パネリスト3者が、少子高齢化が世界に類を見ない速度で進む日本で、労働力の維持・確保という側面から、自社でのダイバーシティ推進や働き方改革への取り組み、それにより社内でどのような効果があったかについてプレゼンテーションを行った。
続きはこちら
SDGsが企業価値の評価基準に
 |
サステナブル・ブランド国際会議2018東京で開催された「ESG/SDGs時代における共有価値の創造」セッションには、進行役として伊藤園の笹谷秀光常務執行役員CSR推進部長、スピーカーとして一橋大学大学院国際企業戦略研究科の名和高司特任教授、住友化学の新沼宏常務執行役員、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の吉高まり主任研究員が登壇した。
続きはこちら
ソーシャル・ファイナンス新時代へ
 |
社会的インパクト投資の一つである「ソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)」やベンチャーフィランソロピーなどが始まり、社会のお金の流れが変わりつつある。「社会課題解決のためのソーシャル・ファイナンスの新時代をどう創るのか」のセッションでは、日本ファンドレイジング協会の鵜尾雅隆代表理事を進行役に、社会的投資推進財団の工藤七子常務理事、ソーシャル・インベストメント・パートナーズの白石智哉共同代表理事、三井住友銀行の上遠野宏成長産業クラスターグループ長がソーシャル・ファイナンスをテーマに議論を深めた。
続きはこちら
働き方改革を支える新たなオフィス環境
 |
サステナブル・ブランド国際会議2018で開催されたセッション「2030年に向けてあるべきGood Workplaceを考えるーー働き方改革を支える新たなオフィス環境」には、スピーカーとして三井不動産法人営業統括部の川路武氏、ワイス・ワイス営業部企画開発課の野村由多加チーフ、イトーキ商品開発本部ソリューション開発統括部Ud&Ecoソリューション開発部の八木佳子部長が登壇した。ファシリテーターは、森林保全活動を行う「一般社団法人more trees」の水谷伸吉事務局長が務めた。
続きはこちら
特集:サステナブル・ブランド国際会議 2018 東京 (2)はこちら











