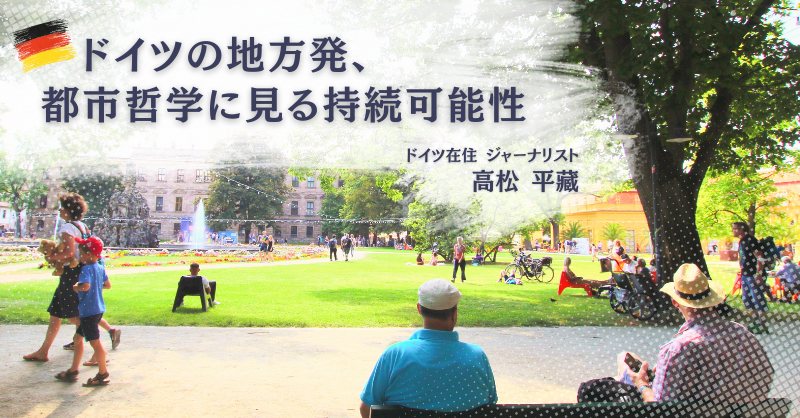 |
日本では「ウォーカブルなまちなか」の形成が大きな課題になっている。そこに至る前の「準備」にあたるのが、ヒューマンスケールという概念だろう。これはクルマ中心社会のあり方への反省から、日本では1990年代に注目された。
この流れ、ドイツではひと足早かった。旧西ドイツでは第二次世界大戦後、1950〜60年代にかけて自動車交通のために都市を最適化する「クルマに優しい都市」を志向した。クルマは経済成長と繁栄の象徴だったのだ。
しかし、環境汚染や騒音、歩行者や自転車の通行が軽視されるといった悪影響が出てくる。とりわけ、小売店が集中する市街中心地で歩行者とクルマの共存が難しくなったことは、多くの人々にとってクルマ社会の弊害を「実感」する出来事だったに違いない。
■市街中心地に歩行者ゾーンはある
今日、多くの自治体には歩行者ゾーンがあるが、「市街中心地」に作られることがほとんどだ。ここは通常、自治体の発祥地である。例えば中世のドイツ都市は市壁で囲み、そして中身が作られた。元々防護壁だが、時代が下がるにつれて撤去されたり、歴史的建造物として保護されている。そして都市自体、市壁の外へも広がった。
そんな経緯があるため、市街中心地は歴史的建物が景観のアンサンブルを形成している。戦後は復興や経済振興が進む一方で、その申し子のようなモータリゼーションへの批判とともに、「都市の歴史」が再発見された。このため中心市街地は「都市のアイデンティティ」「故郷の風景」となって、保護されることになった。
しかし、「博物館」になったのではない。古い建築物の中身はファストフードやアップルストアに至るまで、時代に応じた飲食店や小売店、オフィスに使われている。さらに、中心市街地には広場や市役所などもあり、「自治体のへそ」のような場所だ。このような空間構造は北米でも基本的になく、日本からも想像がしにくい。ドイツの専門家の間でも独自のものと考えられているようだ。
■10年以上かけて作られた歩行者ゾーン
 エアランゲン市の歩行者ゾーン。多くの人にとって400〜500メートルが歩くのに許容できる距離と言われている。その点から言えば、同市の歩行者ゾーンは理想的だ(筆者撮影)
|
筆者が住むエアランゲン市(人口約12万人、バイエルン州)にも歩行者ゾーンがある。ご多分に漏れず、中心市街地にあるのだが、メインストリートの全長が約1.2キロ、そのうち約500メートルが歩行者ゾーンである。途中で枝のように歩行者ゾーンが一部横へ伸びていたり、広場や庭園とも連結している。そんな中に小売店やレストラン・カフェのほか、銀行やオフィス、クリニックなどもある。またベンチが適度に置かれ、前回お伝えしたように、木々も植えられている。
ここで同市の歩行者ゾーンができた経緯を見ておこう。クルマ社会が進む1970年代に深刻な交通渋滞と駐車場不足が明らかになり、1973年に市街中心地の歩行者ゾーン導入の再開発計画が決定された。メインストリートは南北に走っているが、東西にどのようにクルマを横断させるかが大きな問題のひとつだった。ほどなくして土曜日になると、メインストリートを車両止めにした「実験」が行われた。実験ゆえに毎回車両止めが異なる。当時を体験した市民は「なんてこった、今週はここが通れなくなっている!」といら立たせられることも多かったようだ。
紆余曲折あり、部分ごとに歩行者ゾーンが拡大され、今日の形になったのが1989年だった。
実は小売店側は、クルマが通行できなくなると客が来なくなるのではないかとの懸念を持ったが杞憂に終わった。
■哲学としての「ヒューマンスケール」とは何か?
約500メートルの歩行者ゾーンの真ん中あたりにトイレがある。これは2014年に市が行ったアンケート調査が基になっている。歩行者ゾーンに対する満足度は全体的に高いものだったが、不満に挙がったのは、子どもが遊べない、トイレがない、というものだった。この調査を見ると、人々は歩行者ゾーンをまるで公園のように感じていると推測できる。そして、できたのがこのトイレだった。
言い換えれば「ウォーカブル」とは道を公園のような空間にすると考えれば良いのではないか。「細長い公園」である。道路とは一般に物流とモビリティが中心になった「クルマが王様」の空間だ。それに対して、歩行者ゾーンは誰もが滞在し、体験し、出会う場所として包摂性の高い公共空間のモデルになっている。
こうしたヒューマンスケールの公共空間(=歩行者ゾーンのある中心市街地)の条件としてドイツでよく挙がるのが「滞在の質」「アクセスのしやすさ」「提供内容の多様性」の3つである。
まず、滞在の質は都市の公共空間の魅力や生活の質を指し、清潔さ、安全性、緑地、ベンチ、広場などによって高まる。これによって、人々を街に誘い、社交や知り合う機会ができる。
次に、アクセスのしやすさは「自治体のへそ」である都市中心部へのアクセスの容易さを示す。公共交通機関との接続、駐車スペース、自転車道などの質が重要で、これによって中心市街地の利用しやすさを左右する。
最後に、提供内容の多様性は小売店・レストランなどの多さ、そして消費活動のみならず、フェスティバルなどの文化プログラムのバリエーションの多さを指す。文化プログラムについては、別の機会に詳しく述べるが、プログラムの良さはドイツの自治体ごとに文化政策が充実している点も大きい。いずれにせよ、これらが都市の魅力を高める。
この3つの要素は相互に関連しているため、どれかが欠如すると悪循環を招く。3つの要素を常に注視し、調整することが重要だ。
ドイツの歩行者ゾーンは、ドイツ独自の中心市街地という構造をベースに作られ、日本とは前提が異なる。しかし、「滞在の質」「アクセスのしやすさ」「提供内容の多様性」を汎用性のある価値と考え、「問い」とした時、あなたが住む町はどのように評価できるだろうか? ぜひ試してみていただきたい。

高松 平藏 (たかまつ・へいぞう)
ドイツ在住ジャーナリスト
ドイツの地方都市エアランゲン市(バイエルン州)および周辺地域で定点観測的な取材を行い、日独の生活習慣や社会システムの比較をベースに地域社会のビジョンを探るような視点で執筆している。日本の大学や自治体などでの講義・講演活動も多い。またエアランゲン市内での研修プログラムを主宰している。 著書に『ドイツの地方都市はなぜクリエイティブなのか―質を高めるメカニズム』(学芸出版)をはじめ、スポーツで都市社会がどのように作られていくかに着目した「ドイツの学校には なぜ 『部活』 がないのか―非体育会系スポーツが生み出す文化、コミュニティ、そして豊かな時間」(晃洋書房)など多数。 高松平藏のウェブサイト「インターローカルジャーナル」















